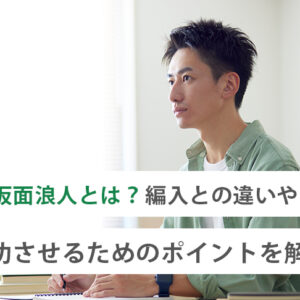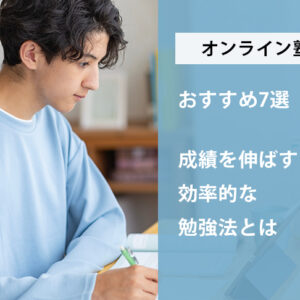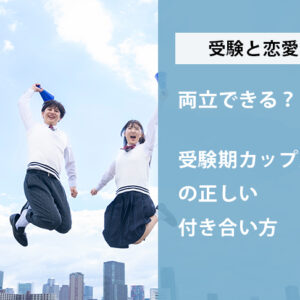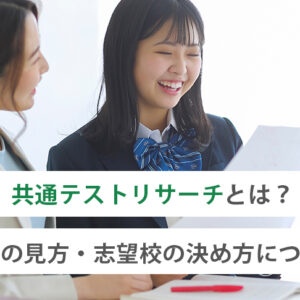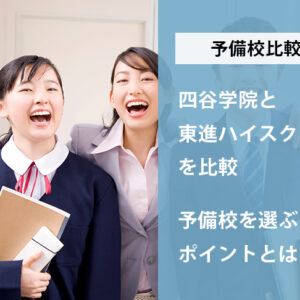志望校をいつまでに決めるかは、受験の成功を左右する重要なポイントです。しかし、志望校選びに悩む人は少なくありません。決断が遅れると対策が後手に回り、思うような結果が得られない可能性もあります。
効果的に受験準備を進めるためにも、何を基準に志望校を決めるべきなのか志望校選びのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
大学は「どこに行くか」ではなく「何をするか」が大切

大学選びで後悔しないためにも「どの大学に行くか」ではなく、「その大学で何を学び、どのような経験を積むか」という点を意識することが大切です。偏差値や知名度だけで判断するのではなく、カリキュラムの内容や実践的な学びの機会を重視することで、充実した大学生活につながります。
たとえば、専門分野の講義内容や研究環境を確認し、自分の学びたいことが実現できるかを判断するようにしましょう。
また、大学での学びを将来どのように活かすかを考えることも重要です。大学時代の経験は、その後のキャリアや人生に大きな影響を与えます。知識を深めるだけでなく、課題解決能力やコミュニケーション力を身につけることで、社会人になった際に適切な選択を行えるようになります。
そのため、大学を「ゴール」とするのではなく、その先を見据えた学びの場と捉えるようにしましょう。
【学問編】大学の志望校の決め方

全国には多数の大学があり、学部や学科も豊富に存在します。そのため、志望校を決めるのに迷うのも無理はありません。
ここでは、興味のある分野や将来の職業を基に志望校を決定する2つの方法について紹介します。
自分の興味のある分野を学べるか
大学選びでは、自分が学びたい分野を深く学べる環境かを確認するようにしましょう。大学ごとに、カリキュラムや専門分野の充実度は異なります。そのため、学科の内容・研究テーマを確認し、自分の興味に合うかを判断するようにしてください。
もし、興味のある分野がはっきりしない場合は、「楽しいと感じること」や「得意なこと」を考えてみるとよいでしょう。たとえば、ものづくりが好きなら工学系、社会問題に関心があるなら経済学や社会学など、自分の特性に合った分野を見つけてみてください。
(大学選びの参考例)
生徒Aさんは、子どもの頃からコンピューターやプログラミングに興味がありました。特にAI(人工知能)や機械学習に魅力を感じ、最新技術を学ぶためにAI学科のある大学への進学を決めました。
将来就きたい職業に直結する学部があるか
将来の職業を意識して大学を選ぶことも、進路決定において重要なポイントです。たとえば、医師や薬剤師などの資格が必要な職業は、専門分野を学べる学部に進学しなければなりません。そのため、まずは自分が将来就きたい職業を明確にし、それに必要な学部や資格についてリサーチしましょう。
また、大学によってはインターンシップや実習の機会を提供しており、これらの経験は就職活動において大きな強みになります。学ぶ内容だけでなく、実践的な経験を積める環境が整っているかも確認するとよいでしょう。
(大学選びの参考例)
生徒Bさんは幼い頃から環境問題に関心があり、将来的には環境保護団体で働きたいと考えていました。そこで、自分の関心を深めるために、環境学や持続可能な開発に関する学問が学べる大学を探しました。
【環境編】大学の志望校の決め方

大学の志望校を決める際には、学ぶ内容以外にも「環境」を留意すべきです。以下では、志望校を決める際に確認すべき環境について紹介します。
大学の特色が自分に合っているか
大学選びでは、キャンパスの環境や学生生活が自分に合っているかを確認することが大切です。都市部にある大学と自然に囲まれた大学では、雰囲気や生活スタイルが大きく異なります。
また、研究施設の充実度や教育スタイルも重要なポイントです。たとえば、最新の設備が整った研究機関がある大学や、少人数教育で手厚い指導が受けられる大学など、自分の学び方に適した環境を選ぶことで、より充実した大学生活を過ごせます。オープンキャンパスに参加したり、在学生の声を参考にしたりしながら、自分に合う大学を見極めましょう。
課外活動やサークルが充実しているか
大学では、学問だけでなく課外活動を通じた経験も得られます。サークルや部活動、ボランティア活動などに参加することで、協調性・リーダーシップ力を養えるでしょう。これらの経験は、将来のキャリアや人生においても大きな影響を与えます。
また、大学ごとにサークルやイベントの特色が異なります。全国大会を目指す体育会系の部活動が盛んな大学もあれば、文化系サークルやボランティア活動が充実している大学もあります。
通学が負担にならないか
大学の場所によっては、通学時間や交通費が大きく異なります。毎日通うことを想定して、通学の負担が少ないかを確認しましょう。通学時間が長すぎると、勉強や課外活動の時間が削られ、大学生活の充実度にも影響を与えます。
また、大学が自宅から遠い場合は、一人暮らしや下宿についても検討する必要があります。その場合、生活費や家賃の負担がどの程度必要になるのか、家族と相談しながら決めるようにしてください。
また、集中して学べる環境なのか判断するためにも、大学周辺の住環境や治安、生活に必要な施設の有無なども事前に調べておくことをおすすめします。
学費や生活費が無理なく負担できるか
大学進学には、学費だけでなく通学費や生活費もかかります。一人暮らしをする場合は、家賃や食費、光熱費などの負担も考慮し、無理のない範囲で進学先を選ぶことが大切です。
また、奨学金制度や学費免除制度を利用できるかも調べておきましょう。大学によっては、学費サポート制度が充実している場合もあります。経済的な負担をできるだけ抑えながら、自分に合った学びの環境を整えましょう。
志望校選びでよくある失敗
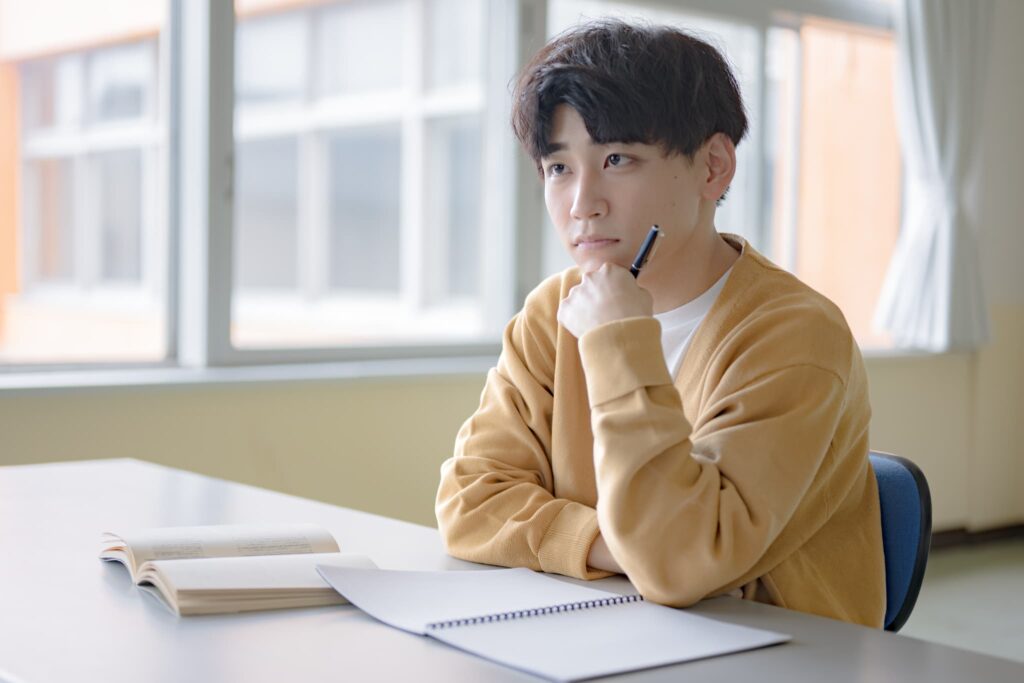
志望校を選ぶ際に、「友達も行くから」「有名な学校だから」といった周囲の影響や表面的な理由で決めてしまうのは避けるべきです。そのような理由で進学すると、大学で学びたいことが見つからず、学業や将来の進路に対するモチベーションが低下してしまいます。
また、偏差値だけを基準に志望校を決めるのもおすすめしません。偏差値が高い大学に入っても、自分の興味や目標に合っていなければ、学びに充実感を得られないケースもあります。
大学選びでは、偏差値にとらわれすぎず、「自分は何を学びたいのか」「将来どのような道に進みたいのか」を明確にし、それに合った大学を選ぶことが大切です。自分の興味や将来の目標に合った大学を見つけられれば、より充実した大学生活を過ごせます。
大学の志望校はいつまでに決めるべき?
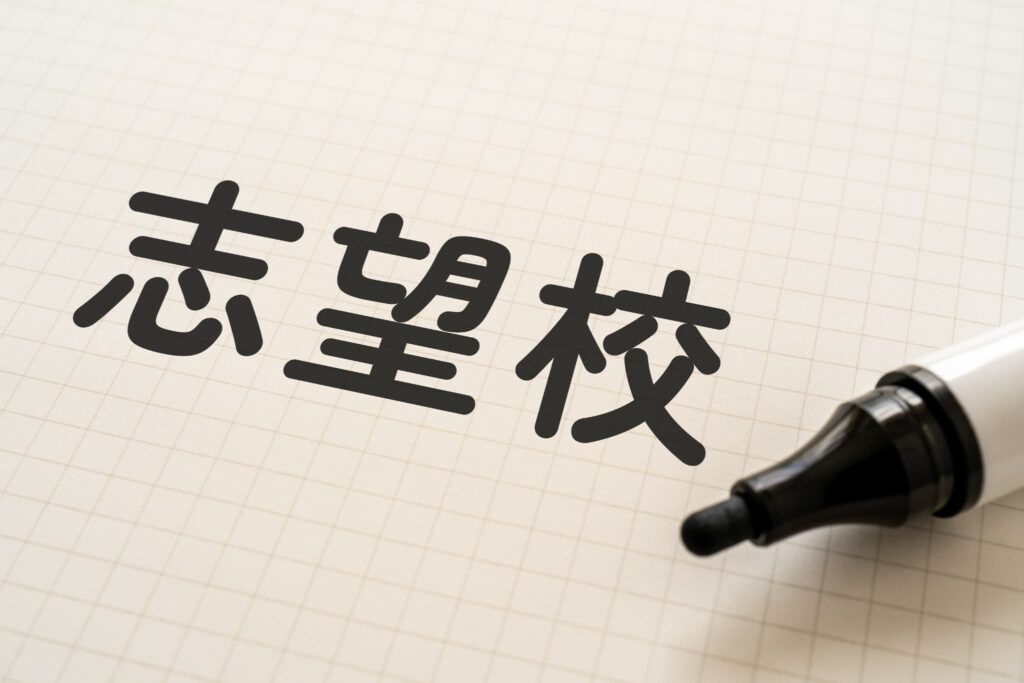
大学の志望校は、遅くとも高校2年生の冬までに決めるのが理想です。早めに決めておくことで、高校3年生から、志望校の入試形式に合わせた対策や模試の活用に集中できます。
多くの学生は、高校2年生の7月~翌年3月にかけて第一志望を決めています。この時期に志望校を明確にすれば、受験勉強の計画を立てやすくなり、志望校合格に向けた効率的な学習を行えるでしょう。
自分に合った志望校を決める3ステップ

最後に、志望校を決める際の具体的な3つのステップを紹介します。この順番で進めればスムーズに候補を絞ることができるので、ぜひ参考にしてみてください。
1.大学の情報収集と比較を行う
自分に合った志望校を決めるには、まず大学の情報を集め、比較することが大切です。
自分の興味や将来の目標に合った学部・学科がある大学を3~4校ほどピックアップし、それぞれの特徴を詳しく調べてみてください。具体的には大学の公式サイトやパンフレットを確認し、カリキュラムの内容、教育方針、取得できる資格、卒業後の進路などを比較すると役立ちます。
また、学費や奨学金制度の有無、キャンパスの設備など、学習環境についても事前に把握しておきましょう。さらに、通学のしやすさや大学周辺の住環境も考慮することで、入学後の学生生活を具体的にイメージしやすくなります。こうした情報を総合的に判断したうえで自分に合う大学を選ぶことが、充実した大学生活への第一歩となるでしょう。
2.オープンキャンパスや学校説明会に参加する
オープンキャンパスや学校説明会に参加することで、大学の雰囲気を把握できるようになります。実際にキャンパスへ足を運べば、施設の充実度や学生の雰囲気、授業の進め方などを肌で感じられます。
さらに、学科担当の教員や在学生と直接話すと、学びの内容や大学生活に関するリアルな情報を得られます。授業の難易度やゼミの雰囲気、就職支援の充実度など、パンフレットではわからない細かい部分まで確認できるため、志望校選びの貴重な判断材料となるでしょう。
3.受験計画を立てて最終的な志望校を決定する
情報収集やオープンキャンパスへの参加を終えたら、受験計画を立てて最終的な志望校を決定しましょう。受験計画を立てることで、合格に向けて必要な勉強内容や確保すべき学習時間を把握できるようになります。
また、受験日程や出願期限を確認し、準備が間に合うかも検討しましょう。志望校によっては推薦入試やAO入試など多様な受験方式があるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。さらに、模試の結果を参考にしながら、合格の可能性を現実的に判断するのも重要です。
まとめ
本記事では、志望校の決め方やいつまでに決断するのがよいかを紹介しました。大学選びは慎重に行い、自分の将来の目標と照らし合わせながら決めることが大切です。志望校を決めたら、受験準備を万全に整えるために計画的に勉強を進めましょう。
効率よく学習を進めるには、塾や予備校を活用するのも有効です。専門的な指導を受けることで、苦手分野の克服や志望校対策を強化できます。塾・予備校を探している方は、「オススメ予備校一覧ページ」をチェックして、自分に合った学習環境を見つけてください。