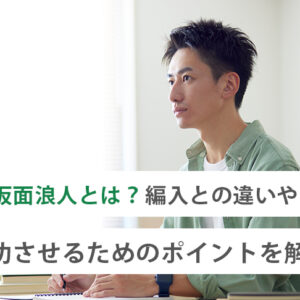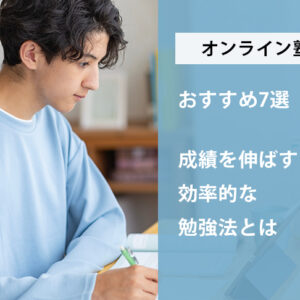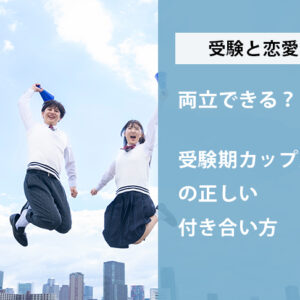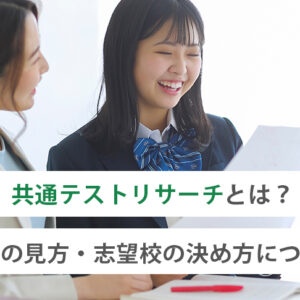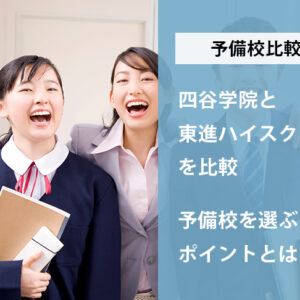高校生が勉強しない背景には、単なる「怠け」ではなく、将来への不安や学習環境が整っていないことなど、さまざまな要因が複雑に関わっています。親が感情的に叱ったり、無理やり勉強させようとすると、かえって逆効果となる場合もあるでしょう。
保護者は、あくまでも子どもが自発的に勉強に取り組めるように、サポートする姿勢が大切です。
本記事では、保護者が日常生活でできる働きかけや、適切なコミュニケーション方法について、詳しく解説していきます。
高校生が勉強しない理由とは

高校生のなかには「勉強しなければ」と思いつつも、なかなか行動に移せない子どもが多くいます。以下では、高校生が意欲的に勉強に取り組めない背景について、見ていきましょう。
勉強に対する意欲が湧かない
高校生が勉強しない理由のひとつに、「やる気が出ない」という点が挙げられます。たとえば、過去の経験から勉強に苦手意識や嫌悪感を持っている場合、「どうせ自分には無理だ」と思い込み、やる前から諦めてしまうケースがあるでしょう。さらに、授業の進行スピードについていけず、内容が理解できないまま進んでしまうと、苦手意識がますます強くなります。
また、「何のために勉強するのか」といった目的や将来の目標が明確でないことも、大きな要因のひとつです。進学や就職など、具体的な目標がなければ、勉強する意味がないと感じてしまうでしょう。
勉強を始めても長く続けられない
やる気を出して一度は勉強を始めたとしても、なかなか継続できないのも高校生によく見られる悩みです。その背景には、集中できる環境が整備されていないことが原因のひとつと考えられます。たとえば、勉強机にスマホやゲームを置いていると、つい手を伸ばしてしまいがちです。
また、「勉強しなさい」と親や先生から強くいわれると、反発心が生まれやすいものです。自分の意志でなく、他人に強制されたと感じると、勉強に対するモチベーションは自然と下がってしまいます。
勉強しない高校生の末路
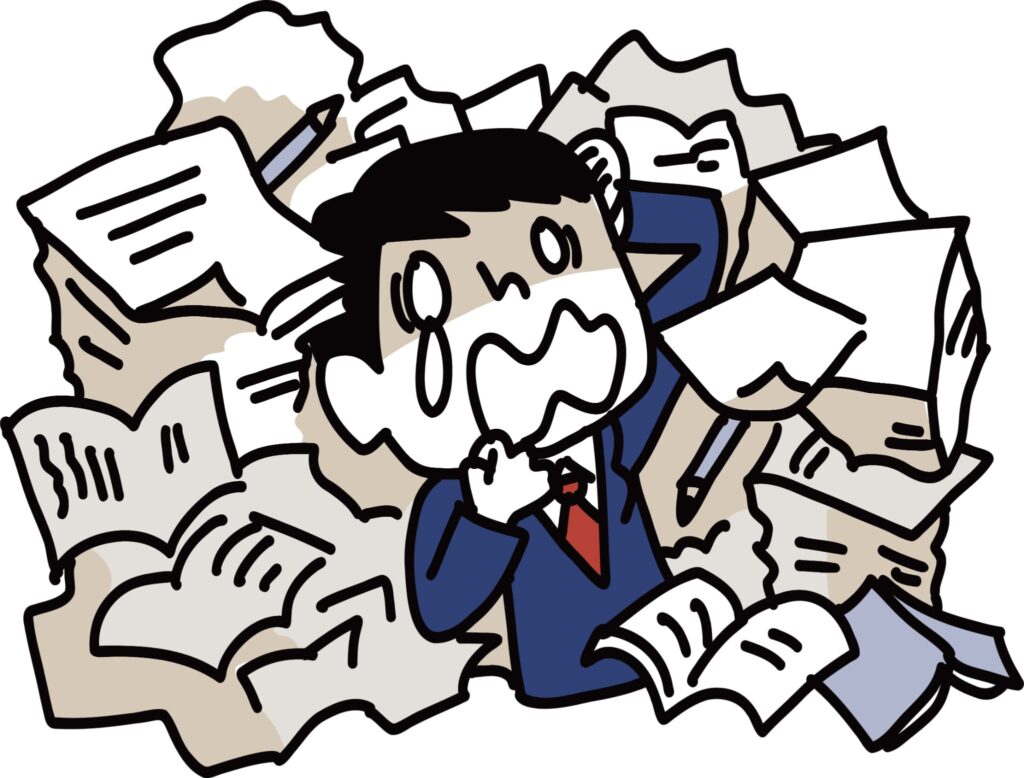
勉強をしない状態が続くと、高校生活だけでなく、進路にも大きな影響を与える可能性があります。以下では、勉強しないことで直面する具体的な問題について見ていきましょう。
学力が低下する
勉強しない期間が続くと、学力は徐々に低下していくものです。最初は少しだけの遅れだったはずが、経過とともに周囲と差が開いていきます。そうなれば、徐々に授業内容を理解できなくなり、定期テストや模試での点数も下がってしまうでしょう。
このような状態が続くと、勉強に取り組むことが苦痛になり、「どうせできないから」と諦めるのが癖になってしまうこともあります。
こうした感情は、学力の回復だけでなく、高校生活にも悪影響を及ぼすでしょう。
進級・進学に影響する
勉強を続けていないと、学力の低下だけでなく、進級や卒業にも影響が出てきます。定期テストや単位の取得状況によっては、留年する可能性もあるでしょう。このような状況に追い込まれると、自分を責めたり、周囲との関係が悪くなったりして、精神的に大きな負担を抱えてしまうものです。
なかには、自分に対する否定的な感情が強まり、学校へ行きづらくなってしまう子もいます。さらに、進学に必要な学力や内申点が足りず、希望する大学への進学を諦めざるを得なくなる可能性もあるでしょう。
高校生が勉強を取り組むために親ができるサポート方法
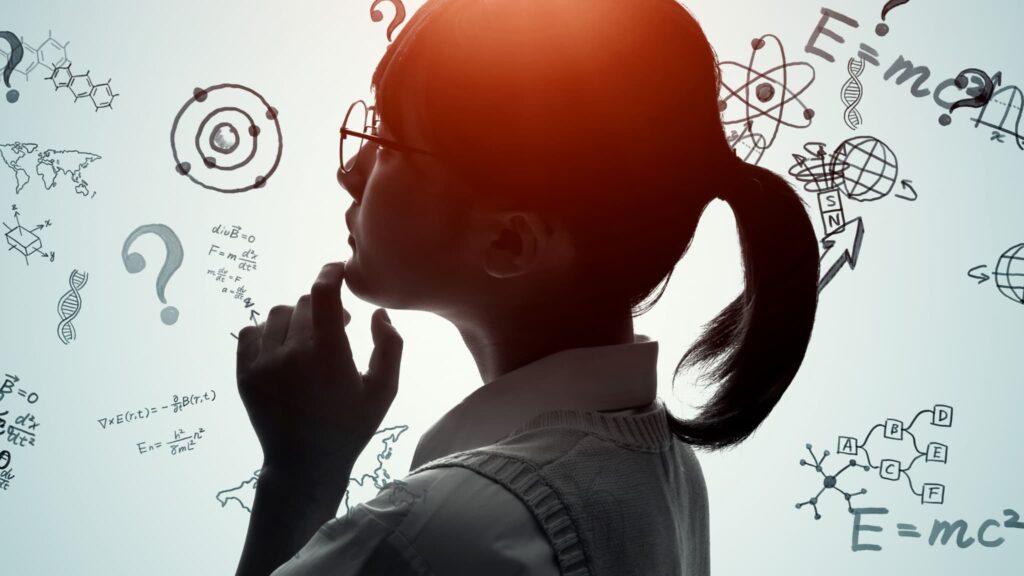
高校生が自分から勉強に取り組まない場合、親の関わり方次第で改善できることもあります。以下では、親ができる3つのサポート方法について見ていきましょう。
勉強を強制せず、学習意欲を引き出す
高校生は自立心が芽生える時期でもあり、頭ごなしの指示には反発しやすいものです。そのため、勉強を強制するのではなく、子どもが自分から取り組むようにサポートすることが大切です。
まずは、子どもが何に悩み、どんなことに躓いているのかを丁寧に聞くことから始めましょう。たとえば、「授業がわからなくてつまらない」「やる意味がわからない」といった場合には、しっかり意見を聞いたうえで一緒に考えることが大切です。
集中できる学習環境を整える
勉強への意欲があっても、集中できる環境が整っていなければ継続は難しくなります。現代の高校生にとって、スマートフォンやゲームなどの誘惑がたくさんあります。それらに気をとられてしまうと、勉強時間が極端に短くなるでしょう。
まずは、スマホの使用時間にルールを設けることが効果的です。たとえば、「○時以降はリビングで保管する」といったように、家庭内での約束を明確にしましょう。
また、ゲームも時間を決めて遊ぶことで、ON/OFFのメリハリがつけやすくなります。さらに、落ち着いて勉強に取り組める環境を整えてあげることも大切です。たとえば、リビングの一角でも、余計なものが視界に入らないように工夫するだけで集中しやすくなることが期待できます。
小さな成功体験で自信を育ませる
勉強に取り組むことに前向きになるには、「やればできる」という成功体験が必要です。
成功体験を得るためにも、子どもにとって達成可能な小さな目標を一緒に設定するようにしましょう。たとえば、「今日は英単語を10個覚える」など、短時間で終わるタスクを提示すると、取り組みやすくなります。そして、努力の過程をしっかり見守り、結果だけでなく「続けたこと」「工夫したこと」を認めてあげることが自信につながります。
親がやりがちなNG行動

子どもに勉強してほしいという思いから、逆効果な関わり方をしてしまうことがあります。そうなれば、勉強をしないだけでなく、子どもとの関係に亀裂が生じかねません。
以下では、子どもが勉強への意欲を損なうNG行動について紹介します。
叱る・強制する
子どもが勉強しないと、つい「なんでやらないの」「さっさとやりなさい」と叱ってしまうことがあるかもしれません。しかし、こうした言動は、子どもにとって大きなストレスになりやすく、勉強に対する苦手意識や抵抗感を強めてしまいます。
また、「勉強しなさい」と強制されることで、反発したくなる気持ちが生まれがちです。その結果、机に向かうことを避けるようになり、勉強を「嫌なもの」「やらされるもの」と認識してしまいます。
ご褒美や罰で勉強させようとする
「テストで高得点をとったらお小遣いをあげる」「やらなかったらゲーム禁止」など、ご褒美や罰を使って勉強させようとするのもNGです。短期的には効果があるように見えますが、長期的な観点でいうと逆効果となる可能性があります。これはご褒美を与えることで、勉強が「報酬を得るための手段」となり、本来の目的や学ぶ楽しさを見失ってしまう可能性があるからです。
また、罰を与えることで一時的に行動を変えられたとしても、勉強そのものに対する嫌悪感やストレスは溜まっていきます。その結果、勉強を避けるようになったり、親子関係が悪化したりするケースも少なくありません。
他の子と比較する
他の子との比較も避けるべき行動です。他の子と比較すると、「自分はダメだ」と感じるようになり、自己肯定感を低下させてしまいます。
また、比較されることでプレッシャーを強く感じてしまう子もいるものです。そうなれば、精神的に大きな負担となり、かえって勉強が嫌いになってしまうことにもつながります。
高校生が自ら勉強に取り組むための環境を作るには

高校生が自分から勉強に取り組むようになるには、ただ「やりなさい」と指示するだけでは足りません。学びやすい環境を整え、自然と勉強に向かえるようにサポートすることが求められます。
以下では、具体的な方法について紹介します。
予備校・塾で学習リズムを作る
高校生が勉強に取り組むためには、予備校や塾を活用するのも効果的です。塾や予備校では、決まった時間に授業が行われるため、生活のなかに自然と学習時間が組み込まれます。毎週のスケジュールに合わせて行動すれば、勉強の習慣が身につきやすいでしょう。学校とは違う環境に身を置くことで、意識が切り替わりやすいものです。
また、同じ目標に向かう仲間や、信頼できる講師の存在も大きな刺激になるでしょう。周囲のサポートがあることで「頑張ろう」という気持ちが芽生えやすくなります。
さらに、個別指導のある塾では、苦手な分野に焦点を当てて学ぶことが可能です。理解できていない教科があっても、一人ひとりのペースに合わせて丁寧に教えてもらえるため、自信を取り戻すきっかけになるでしょう。
継続的な学習の大切さを伝える
どれだけよい学習環境だとしても、勉強は1日で完結するものではありません。自ら勉強する力を育てるには、「継続することの大切さ」を伝えることが重要です。人間は一度学んだことでも、時間が経つにつれて忘れてしまいます。だからこそ、毎日少しずつ勉強を積み重ねることが知識の定着につながるのです。
たとえば「10分でもいいから毎日机に向かう」というルールを決めるだけでも、学習へのハードルが下がり、習慣にしやすくなるでしょう。最初はやる気がなくても、続けることで自然と「やらないと落ち着かない」と思えるようになる可能性もあります。
また、定期的に復習することで学力が向上し、自信を持って問題に向かえるようになるでしょう。親や先生が継続する重要性を丁寧に伝えることで、子ども自身が学びに価値を見いだし、前向きに取り組めるようになるはずです。
まとめ
高校生が勉強しない理由として、意欲の低下や学習環境の問題などが挙げられます。自分から勉強に取り組むようにするには、その背景を理解したうえで、親が適切にサポートすることが大切です。具体的には、叱る・強制するといったNG行動ではなく、学習意欲を引き出す接し方や、集中できる環境作りが効果的といえるでしょう。
また、予備校や塾を活用することで学習リズムが整い、自主的な勉強習慣も身につきやすくなります。子どもに合った学びの場を探す際は、「オススメ予備校一覧ページ」もぜひご覧ください。