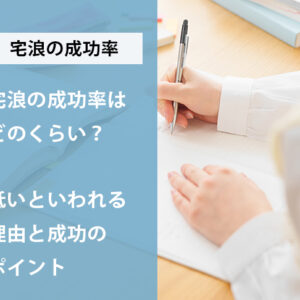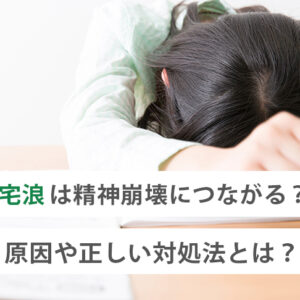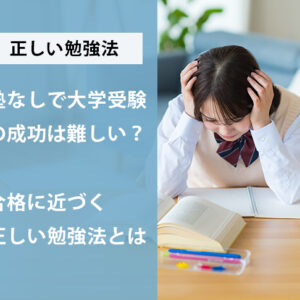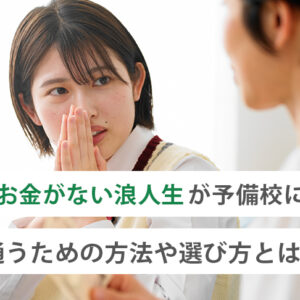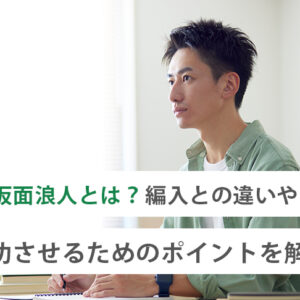勉強を頑張っているにもかかわらず、成績が伸び悩んでいる高校生は少なくありません。
時間をかけているのに成果が出ないと、誰しも不安や焦りを感じてしまいます。実際に、「毎日机に向かっているのに模試の点数が伸びない」「何を優先して勉強すればいいかわからない」といった声は珍しくありません。
勉強法やスケジュールの立て方を少し見直すだけで、勉強の効率は大きく改善できます。
この記事では、成績が上がらない人の特徴を踏まえたうえで、科目ごとの勉強法や勉強スケジュールの立て方までを段階的に解説します。現状を変えたいと考えている高校生は、ぜひ参考にしてください。
勉強しているのに成績が上がらない人の特徴

努力を続けているのに思うように結果が出ない場合、「勉強の仕方」に原因があるかもしれません。
ここでは、成績が伸びない人に共通する4つの特徴を紹介します。
目標や計画を定めていない
「とりあえず勉強しよう」と行き当たりばったりで進めてしまうと、何をどこまで取り組んだか把握できなくなります。
目的が明確でない状態では、モチベーションも維持しづらくなり、やる気が空回りしてしまうでしょう。また、モチベーションが低いまま勉強を続けても、学力は伸びにくいといえます。「次の模試で英語の偏差値を5上げる」「2週間で数学の基礎問題を解けるようにする」といった、具体的な目標を持つことで、取り組むべき内容が明確になります。
さらに、こうした目標を「見える化」するために、部屋の壁に貼ったり、手帳に毎日書き込んだりする方法も効果的です。視覚的に確認できるようにすることで、意識の持続につながります。
集中できていない
学習環境が整っていないと、勉強時間のわりに効果が上がらない状態が続いてしまいます。
例えば、勉強机にスマートフォンや漫画などがあると、勉強に集中できなくなります。集中力を高めるには、スマートフォンを別の部屋に置いたり、静かな図書館や自習室を活用したりするのがおすすめです。
また、「ポモドーロ・テクニック」を活用するのもおすすめです。ポモドーロ・テクニックとは、作業と休憩を交互に行う時間管理術です。具体的には、以下のように時間管理を行います。
・1セット=「25分の作業+5分の休憩」
・これを4回繰り返したあとに、15~30分の長めの休憩を取る
集中力を維持しやすく、効率的に勉強や仕事に取り組める方法として広く活用されています。
アウトプットしていない
インプットばかりの勉強では、知識の定着が進みません。
教科書を読むだけでは「わかったつもり」になりがちで、実際に問題を解くと「わからない」ケースがあります。
知識を確実に定着させるには、自分の言葉で説明するアウトプットの機会が欠かせません。具体的には、演習問題を繰り返すだけでなく、友人に教える・声に出して説明するようにしましょう。
また、オンラインでの解説動画を視聴したあとに、自分でその内容を要約してノートに書き出すのも効率的な学習になります。これにより、記憶の定着と理解の深まりの両方を実感しやすくなります。
復習しにくいノートのとり方をしている
授業中にただ板書を写すだけでは、復習の役に立たないノートになりがちです。あとから見返したときにポイントが整理されていなければ、再確認がしにくくなります。
ノートには、「なぜ間違えたか」「次にどう改善するか」をメモしておくと、単なる記録ではなく思考の履歴として役立ちます。あとで振り返ったときに、自分の成長を感じやすくなる点もメリットです。
復習しやすいノートにするためにも、「色分け」や「図解」を積極的に取り入れましょう。このようなノートにすれば、視覚的にも理解しやすく、記憶の定着にもつながります。
また、間違えた問題をあとから書き加えるなど、自分専用の参考書のように使えるノートを目指してみてください。
【科目別】成績を上げる効率的な勉強法
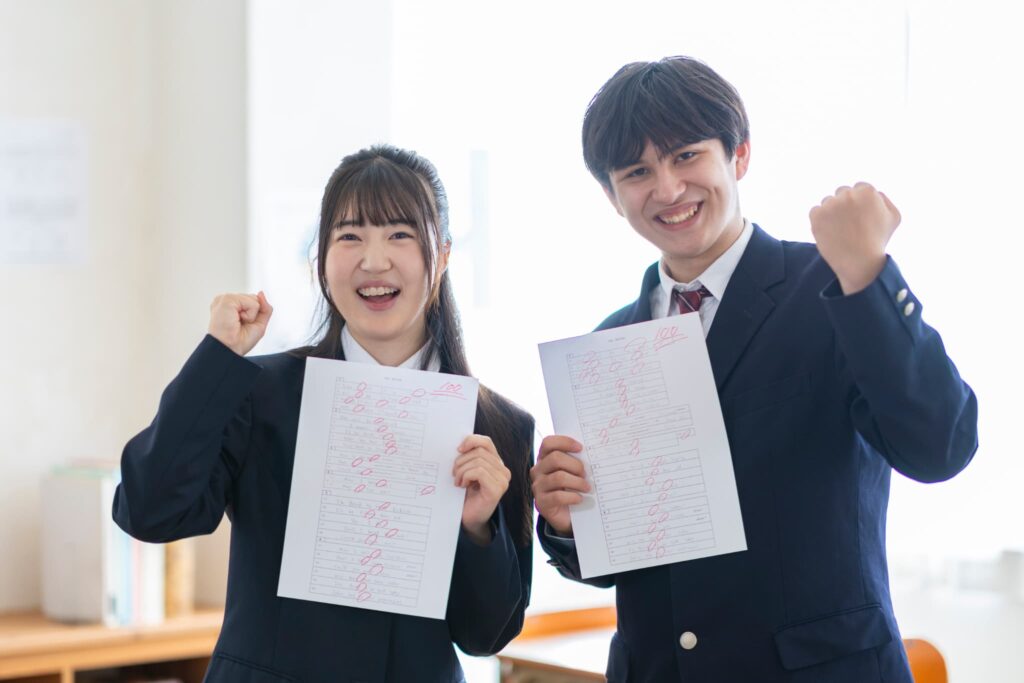
科目によって、効果的な勉強方法は異なります。ここでは主要4教科に絞って、それぞれに合った勉強法を紹介します。
国語:現代文と古典ではアプローチを変える
現代文では問を読む前に本文の構造を把握することが大切です。
段落ごとの要旨をとらえながら読み進めることで、設問に対する根拠も明確になります。一方で、古文や漢文では文法と単語の暗記が土台になります。特に、古文単語や助動詞の意味は、繰り返し復習することで自然と読解力が身に付きます。文学作品の背景や作者の意図を知ることで、設問への理解も深まりやすくなるでしょう。
加えて、現代文の記述問題対策として「自分の意見を書く練習」も有効です。新聞のコラムを読んで要約し、自分の考えを添えてみると、論理的な文章力のトレーニングにもなります。
英語:単語と構文の反復+読解トレーニング
英語は語彙力と文法力をバランスよく鍛えることが重要です。
まずは単語帳や構文集を使って基礎を徹底し、そのうえで長文読解の練習に取り組みましょう。なお、単語帳は複数の本を取り組むのではなく、一冊を完璧にするようにしてください。
文章を読んだら、和訳するだけでなく「主語・動詞・目的語」を意識して構造をつかむ練習をすることが効果的です。長文読解は毎日英語を聞く・読むことで、自然と身に付くようになります。英語ニュースや短文エッセイなどを活用すれば、実用的な表現も学べるのでおすすめです。
音読を取り入れることで、読む力だけでなくリスニング力や発音も向上します。音読は脳の複数の領域を同時に刺激するため、学習効果が高いとされています。
数学:解法の暗記ではなく「なぜそうなるか」への理解
数学の勉強では、問題の解き方をただ覚えるのではなく、計算式の意味や考え方を理解することが重要です。
1問にかける時間を増やしてでも、「どうしてこの式になるのか」を言語化できるようにしましょう。基本問題から応用問題へのステップアップには、基礎の徹底が不可欠です。基礎が定着したと感じたら、応用問題に取り組んでください。なお、問題に取り組むなかで、間違った部分は、ノートに細かく記入するようにしましょう。そうすることで、自分の弱点を把握できるようになります。
過去問を使って出題傾向を把握すれば、戦略的に対策を進めることが可能になります。また、時間制限を設けて問題を解く「模擬試験形式」も有効です。本番さながらの緊張感のなかで問題に向き合うことで、実践力や思考の瞬発力を鍛えられます。
理科・社会:図解で整理する
理科や社会は暗記に頼りがちですが、単純な暗記よりも「関係性の理解」が大切です。例えば、理科ではグラフや図を使って法則の変化を視覚化することで、仕組みをより深く理解できます。
社会では年表や因果関係図を作成すると、出来事同士のつながりが明確になります。ただ覚えるのではなく、ストーリーとして理解することで、記憶の定着が高まるのでおすすめです。
さらに、資料集や地図帳を活用して「情報をリンクさせる」習慣をつけましょう。例えば、地理の知識と歴史の出来事を結びつけることで、より立体的に知識が整理されます。
高校生におすすめ!勉強スケジュールの立て方

毎日の勉強を効率的に進めるには、計画的なスケジュールづくりが欠かせません。ここでは、勉強スケジュールを立てるための3つのステップを紹介します。
STEP1:ゴールを設定する
まずは、具体的な目標を設定しましょう。
目標を立てる際は、短期・中期・長期の3つに分けると、より現実的な計画になります。短期では1週間、中期では1ヵ月、長期では受験までの期間を意識すると、モチベーションを維持しやすくなります。
なお、目標の具体例として、「次の模試で国語の偏差値を5上げる」「2週間で理科の復習を終える」など、数値と期間を明確にすると行動につながりやすくなります。
志望校の試験日から逆算して、年間・月間の計画を作成するのが有効です。スケジュールを立てることで、やるべきことが可視化されるため、迷いなく行動に移せます。
STEP2:1日に費やす勉強時間を決める
平日と休日でメリハリをつけながら、1日当たりに勉強できる時間を決めておきましょう。
「平日は3時間、休日は6時間」といった目安を決めることで、無理なく継続しやすくなります。
集中力のピークは、人によって異なります。無理に長時間勉強しても、効率の悪い勉強になりかねません。そのため、適度な休憩時間も確保したうえで、集中できる現実的なスケジュールを立てましょう。
1日の勉強時間を決める際は、朝・昼・夜どの時間帯に何をするかを意識するのがおすすめです。例えば、「朝は暗記、夜は演習問題」といったように、頭の使い方に応じて時間帯を振り分けてみてください。
STEP3:勉強計画表を作成する
目標と1日の勉強時間が決まったら、週単位・日単位での勉強計画表を作成しましょう。
勉強計画表には、教科ごとの学習内容と量を明記します。「英単語を50語」「数学のチャートを2ページ」など、具体的な数値で記録することで、達成感が得やすくなります。
また、「完了した日付」を記入する欄を設けると、進捗状況が一目でわかります。達成した項目にチェックを入れる習慣をつけると、自然とモチベーションも高まるはずです。
途中でうまくいかないと感じた場合は、週末に見直して調整しましょう。柔軟に対応することが継続のカギになります。
なお、使用するツールは、手帳やアプリを活用してください。作成した勉強計画表をすぐに確認できれば、計画通りに進まなかった際に軌道修正しやすくなります。自身にとって、継続しやすい方法を選ぶようにしましょう。
まとめ
成績を上げるためには、やみくもに勉強するのではなく、目標を持って計画的に取り組むことが重要です。
まずは、自分に合った勉強法を見つけて、実践することからはじめてみてください。自分に合わないと感じる場合は、原因を追究したうえで勉強計画を練り直す必要があります。
「昨日の自分より一つ前進できたかどうか」を意識して、学習を継続していきましょう。
小さな積み重ねが、やがて大きな成果へとつながっていきます。
自身で勉強計画を立てるのが苦手な方は、予備校や塾を活用するのがおすすめです。予備校や塾には、受験に精通した講師が在籍しており、生徒の学力に合わせた勉強計画を練ってくれます。志望校に合格するためにも、入塾を検討してみてはいかがでしょうか。
予備校や塾をお探しの方は、ぜひ「オススメ予備校一覧ページ」をご覧ください。