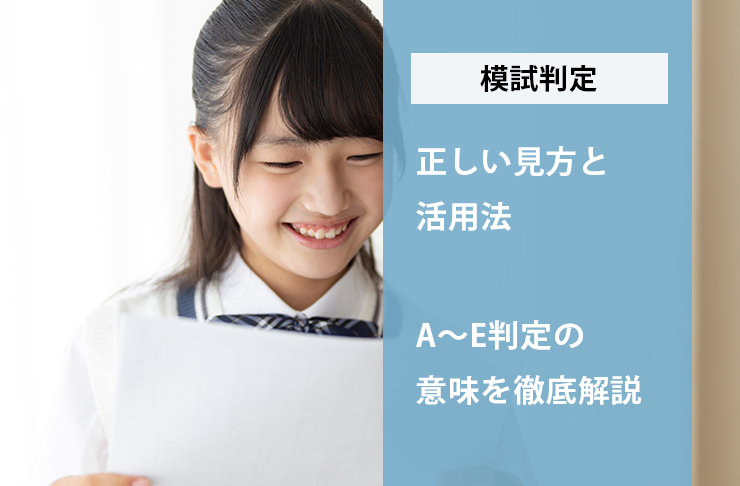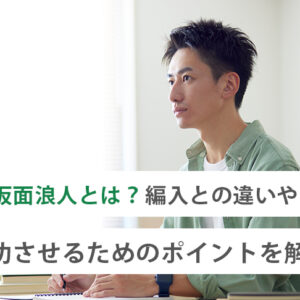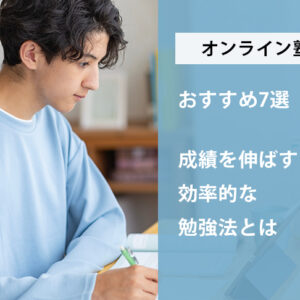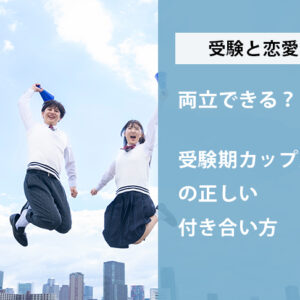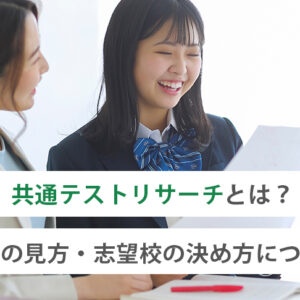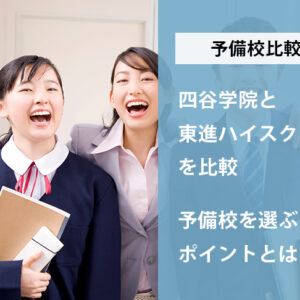模試を受けると返却される「判定結果」は、多くの受験生にとって気になる指標です。しかし、A~E判定の記号や偏差値だけを見て、一喜一憂するのは正しい活用法とはいえません。模試判定は、あくまで「今の学力を示す目安」であり、最終的な合否を決めるものではないからです。
本記事では、模試判定が悪かったときの受け止め方や、A~E判定の意味、判定を正しく見るためのポイントを解説します。さらに、判定を学習に活かす具体的な方法を紹介するため、受験生の方は参考にしてください。
模試判定が悪くても大丈夫!受け止め方のポイント

模試判定が思わしくないと、落ち込んで勉強への意欲をなくしてしまうことがあります。しかし、判定が悪いからといって「不合格」を意味するわけではありません。判定を悲観的に受け止めすぎると、やる気が下がり、学習効率まで落ちてしまう可能性があります。
判定が悪いときこそ、その原因を分析することが改善への第一歩です。学習の基礎が不足していたのか、試験中の時間配分に問題があったのか、あるいは緊張によって実力を発揮できなかったのかを振り返ってみましょう。大切なのは、判定に振り回されて志望校を安易に下げないことです。
偏差値や判定は「今の学力を示すデータ」にすぎず、受験本番までの努力次第で大きく変わります。判定を「合否そのもの」と誤解せず、冷静に受け止める姿勢を持ちましょう。意味を正しく理解できれば、次の模試や勉強に前向きに取り組めます。
なお、模試の結果が悪いときに立ち直る方法について、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
※入稿時に「模試 結果 悪い」の記事リンクを挿入
模試判定の種類と判定基準【A~E判定の意味】

模試の判定結果にはA~Eなどの記号が使われ、合格する可能性のおおよその目安を示しています。ただし、この判定基準は模試ごとに異なるため、同じ偏差値でも結果が変わることがあります。まずは一般的な基準を押さえ、模試の種類による違いを理解しておきましょう。
判定の一般的な基準
多くの模試では、判定はA~Eの5段階で示されます。模試によっては、さらに細かくS判定やF判定が設定されている場合もあります。一般的な合格可能性の目安は、次のとおりです。
| 判定の種類 | 合格する可能性 |
|---|---|
| A判定 | 80%以上 |
| B判定 | 60%以上 |
| C判定 | 40%以上 |
| D判定 | 20%以上 |
| E判定 | 20%未満 |
このように判定の記号は、あくまで目安にすぎません。合否を断定するものではなく、学習を進めるうえでの参考として活用しましょう。
模試ごとに判定基準が異なる
判定は、主催団体によって基準や算出方法が異なります。同じ偏差値でも、河合塾の全統模試、駿台模試、ベネッセ・進研模試では、結果が変わることがあります。これは、受験している生徒の学力層が異なるため、相対評価の仕組みによって判定が動くからです。
そのため、一つの模試だけで合格可能性を判断するのは危険です。複数の模試を受けて総合的に判断することで、自分の実力をより客観的に把握できます。判定基準の違いを理解しておくことが、模試を正しく活用するための第一歩です。
模試の判定結果の正しい見方とは?

模試の本来の目的は、「合否を決めること」ではなく「自分の学力を客観的に把握すること」です。判定結果には、受験勉強を効率よく進めるためのヒントがたくさん含まれています。ここからは、判定をどう見ればよいのかを解説します。
判定だけでなく偏差値や得点分布を見る
模試判定は、志望者全体のなかでの相対的な位置を示しているにすぎません。より大切なのは偏差値や科目ごとの得点状況です。特定の科目で得点が低ければ、その科目を重点的に強化する必要があります。また、得点分布を確認すれば「平均点とどれくらい差があるか」がわかり、集中して取り組むべき分野を絞ることができます。
さらに、得点分布は「自分と同じレベルの受験生がどの問題で得点しているか」を知る手がかりにもなります。周囲との差を把握することで、効率よく点を伸ばす方向性を見つけやすくなります。
判定の推移を見る
模試判定は一度の結果に一喜一憂せず、複数回の推移を見ることが大切です。成績が安定して上がっていれば、努力が成果につながっている証拠です。逆に停滞している場合は、学習方法を見直す必要があります。判定の推移を意識することで、モチベーションの維持や改善点の発見につながります。
推移を記録するときは、グラフや学習記録ノートを使うと効果的です。変化を視覚的に確認できることで学習の手応えを実感でき、日々の勉強を続ける原動力になります。
志望校レベルとのギャップを把握する
模試判定は、「合格可能性」そのものではなく「今の自分の位置」を示すものです。志望校とのギャップを明確にし、あとどのくらい得点を伸ばす必要があるのかを具体的に把握しましょう。その差を埋めるための計画を立てることが、合格に近づく近道になります。
ギャップを分析するときは、過去問の合格者平均点と模試での自分の得点を比べると効果的です。差を数値で認識することで、必要な勉強量や重点的に取り組むべき分野がより明確になります。
模試の判定結果を活かす具体的な方法とは

模試の判定を有効に活用するには、結果をしっかり分析して学習計画に反映させることが大切です。判定をただの「合格可能性の記号」として終わらせず、次につながる具体的な行動に結びつけることが重要です。
科目ごとに弱点を分析する
判定結果を見るときは、全体の判定よりも「どの科目で点を落としたのか」を重視しましょう。例えば、英語では長文読解の得点が低い、数学では図形問題を落としているなど、具体的に弱点を特定することが大切です。単元ごとに苦手を把握できれば、学習の優先順位を決めやすくなります。
弱点を分析するときは、正答できなかった問題を「知識不足」「ケアレスミス」「時間切れ」に分けると効果的です。原因ごとに対策を変えることで、効率よく改善につなげられます。
学習計画を調整する
判定を受け取ったら、それをもとに学習計画を修正しましょう。弱点科目を集中的に補強しながら、得意科目もさらに伸ばすバランスを意識することが大切です。判定を根拠に計画を見直せば、効率よく学力を伸ばせます。特に受験までの残り時間を考慮した、現実的な計画づくりが求められます。
計画を立てるときは「1週間単位の短期計画」と「1ヵ月単位の中期計画」を組み合わせると続けやすくなります。進捗を定期的に確認することで、改善点や修正点も見つけやすくなります。
次回模試に向けて短期目標を設定する
模試判定は結果を確認するだけで終わらせず、次にどう行動するかが大切です。苦手科目については「次の模試で長文問題を20点伸ばす」といった具体的な短期目標を設定しましょう。
模試直後から実行できる内容を組み込むことで、改善につながります。得意科目についても「平均点+10点を安定して取る」などの目標を持つと効果的です。
短期目標は、達成可能な範囲で設定することが重要です。無理のない目標をクリアすることで小さな成功体験を積み重ねられ、次の挑戦へのモチベーションが高まります。
まとめ
模試判定は「合格する可能性の目安」にすぎず、「絶対的な合否」を示すものではありません。判定を見るときは、偏差値や得点の推移もあわせて確認し、結果を冷静に受け止めることが大切です。そして、分析した内容を学習計画に取り入れ、次回の模試や受験本番に活かしましょう。
場合によっては、学習環境を変えることも効果的です。予備校や塾を利用すれば、専門的な指導を受けながら効率よく弱点を克服できます。自分に合った学習環境を見つけたい方は、以下の「オススメ予備校一覧ページ」を参考にしてください。