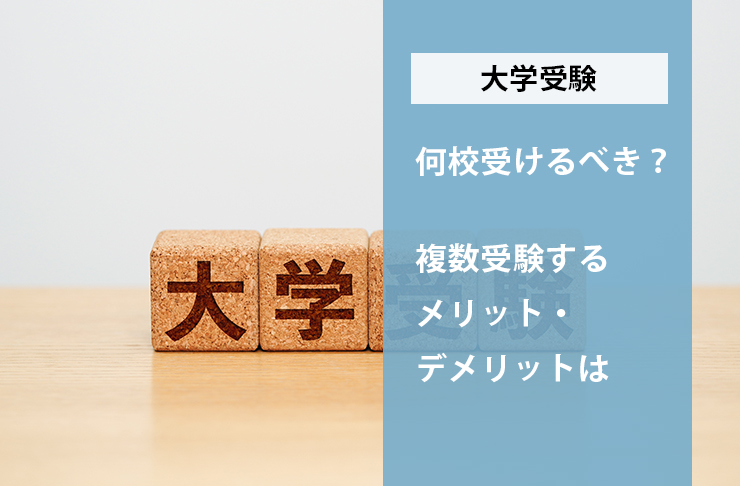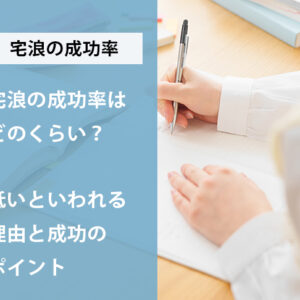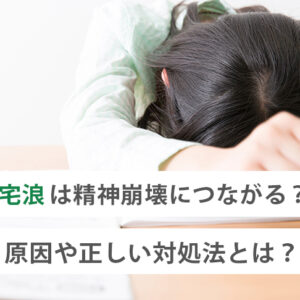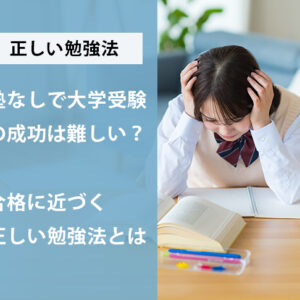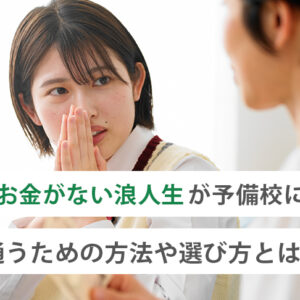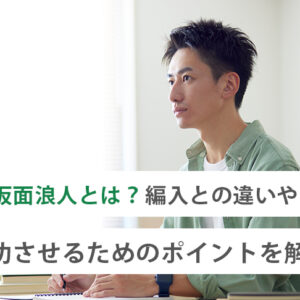受験校を選ぶ際、「何校受けるべきか」と悩む受験生は多くいます。第一志望校に集中したい一方で、不合格のリスクを避けたいという感情は、受験生によくある悩みです。
そこで本記事では、受験校を選ぶ際の考え方や、複数受験するメリット・デメリットを詳しく解説します。あわせて、出願校数を決めるときの判断基準や注意点も紹介するため、納得できる受験計画を立てる参考にしてみてください。
大学受験の受験校を選ぶ際の3つの軸

受験校を決める際は、「安全校」「実力相応校」「チャレンジ校」の3つの軸に分けて考えるのがおすすめです。
・安全校:模試の結果や過去問の手応えから合格の可能性がかなり高いと見込める大学
・実力相応校:現在の学力で合格の可能性が五分五分の学校
・チャレンジ校:偏差値がやや高く、合格できれば大きな達成感を得られる学校
この3つの軸を設定することで、受験計画に安心感が生まれます。安全校を確保することで浪人のリスクを減らし、チャレンジ校で可能性を広げることでモチベーションを維持できます。
併願する際は、どの大学をどのポジションに置くかを明確にすることが大切です。
大学受験でほかの人は何校受験している?

多くの受験生は、平均して3~5校を受験することが多いです。これは、安全校・実力校・チャレンジ校をバランス良く組み合わせた結果といえます。
一方で、受験校を増やすことで合格のチャンスは広がりますが、ある程度を超えて増やしても、負担だけが大きくなる場合があります。
また、国公立大学を志望する場合は、共通テストの結果や個別試験の日程の制約があるため、結果的に3校前後に収めるケースが多くなります。
受験する学校の数は、自分の学力・体力・費用面を踏まえて計画的に決めるようにしましょう。
大学受験で複数の学校を受験するメリット

複数の大学を受けることは、精神面や実践面でのメリットがあります。どこか1校でも合格できるという安心感を得られれば、結果的に本命校の試験にも良い影響をもたらすはずです。
ここからは、大学受験で複数の学校を受験するメリットについて紹介します。
精神面の余裕ができる
複数の大学に出願しておくと、「どこかに受かれば良い」という心理的な安心感が生まれます。第一志望のみを受験する場合は、「失敗できない」という強いプレッシャーがかかり、実力を発揮しにくくなるでしょう。
特に共通テスト後の出願では、結果次第で志望校を再検討する場面も多く、精神的な動揺が大きくなりがちです。あらかじめ複数の学校を想定しておくことで、状況の変化にも柔軟に対応できます。
また、「本命校が不合格でもほかの大学に進学できる」という見通しが立っていると、試験直前の追い込み時期でも落ち着いたメンタルを維持しやすくなります。メンタルの安定は学力の発揮に直結するため、複数の学校を受けることは心理的なリスクヘッジともいえるでしょう。
浪人を回避できる可能性が高まる
複数の学校を受験するメリットとして、浪人の可能性を大きく減らせることも挙げられます。どの受験生も第一志望に合格するとは限らず、安全校を設定しておけば「どこにも受からない」という最悪の事態を防ぐことが可能です。
実際の合格率は、模試判定より低くなる傾向があります。模試ではA判定でも、本番では緊張や体調不良で実力を出しきれないケースもあるため、複数の学校を受験することは確実な進路確保につながります。
また、浪人してしまった場合、翌年の受験費用や予備校費用、生活費といった金銭的負担が生じてしまいます。経済面のリスクを最小限に抑えるという点でも、複数受験は賢明な選択といえるでしょう。
受験本番の雰囲気に慣れられる
受験本番は、どれだけ準備をしても独特の緊張感があります。複数の学校を受けることで、試験会場の空気感や試験監督の指示、時間配分などを実際に体験でき、本番に強くなります。
1校のみを受ける場合、本命校が初めての受験となり、慣れない環境で本来の力を発揮できないかもしれません。事前に似た形式の大学を受験しておくことで、時間の使い方や回答順序を調整できます。
また、大学ごとに出題傾向や難易度が異なるため、ほかの大学の試験経験を通じて自分の得意・不得意を把握できる点も大きなメリットです。経験を重ねることで「自分はこれくらいの問題に強い」という手応えが得られ、本命受験での落ち着いた対応につながります。
大学受験で複数の学校を受験するデメリット

複数の大学を受験することはメリットだけでなく、デメリットもあります。受験日が続けば、体力的・経済的な負担が大きくなるため、計画的に出願校を選ぶことが重要です。
以下では、大学受験で複数の大学を受験するデメリットについて紹介します。
体力面で負担になる
受験シーズンは1~3月にかけて続き、連日の移動や早起きで体力を消耗します。特に地方から首都圏や関西圏の大学を受験する場合は、朝早く出発したり前泊したりすることが多く、睡眠不足にもなりやすいです。
試験日が連続すると集中力も低下し、1校目・2校目は順調でも、終盤で疲労が蓄積して実力を発揮できない可能性があります。
また、受験会場では待機時間が長いことも多く、冬場は気温差によって体調を崩す受験生も少なくありません。受験校が多いほど日程調整や休息時間の確保が難しくなるため、スケジュールの立て方が重要になります。
受験校の数を決める際は、「どの大学を本命とするか」「どの大学を練習目的とするか」を明確にし、優先順位をつけるようにしましょう。
費用がかかる
受験料・交通費・宿泊費など、受験には多くの費用が発生します。一般的な私立大学では1校あたり3~5万円程度の受験料がかかり、5校受けるとそれだけで20万円を超えることもあります。さらに、遠方受験の場合は新幹線代やホテル代が加わり、トータルでは30~40万円になることも珍しくありません。
受験校の数が増えるほど、家計への負担も大きくなります。また、試験に合わせて教材購入や過去問コピー、模試受験などの学習費も増える傾向があります。こうした費用が重なると、予想以上に出費が膨らむため、早い段階で費用試算を行うことが必要です。
家庭によっては「遠方受験を1校に絞る」「同地域の大学に集中する」などの工夫をすることで負担を軽減できます。経済的余裕と合格可能性のバランスを取ることが、最適な受験数を決める鍵です。
複数の学校を受験する際の注意点

複数受験を計画する際は、日程管理や学習範囲の整理を徹底することが欠かせません。どんなに準備を重ねても、スケジュールや科目選定が不十分では力を発揮しにくくなります。
試験日程が被らないようにする
併願校を決める際は、試験日が重ならないように注意しましょう。志望度の高い大学が同日に重なると、どちらかを断念せざるを得ません。
また、試験当日の移動時間や前泊の必要性も含めて計画を立てましょう。同レベルの大学では試験日が近いケースもあるため、出願前にスケジュールを綿密に確認することが重要です。
近年では、オンライン出願サイトや受験スケジュール管理アプリなども活用でき、日程管理のミスを防ぎやすくなっています。紙のカレンダーだけでなく、デジタルツールを併用して「試験日・合格発表日・入学金納付期限」まで一覧化しておきましょう。
また、国公立大と私立大を併願する場合は、共通テスト利用入試の締切日や個別試験の時期が異なります。出願ミスを防ぐためにも余裕を持った計画が欠かせません。
対策範囲を広げないようにする
大学ごとに入試科目や出題傾向が異なるため、あまりに多くの大学を受験すると対策範囲が広がり、効率が下がります。英語・国語・数学の3科目に加えて小論文や面接が必要な大学もあり、準備が分散すると得点力が伸びにくくなります。
そのため、出題傾向が似ている大学を選ぶのが効果的です。例えば、英語重視の大学群・国語を含む3教科型・理系で数学配点が高い大学群など、特徴をそろえることで効率的に対策できます。
また、複数の学校を受ける場合でも、「共通テスト利用入試」や「共通問題を採用する系列大学」をうまく組み合わせると、対策負担を軽減可能です。
加えて、受験科目を統一することで、勉強計画の立案も容易になります。自分の得意科目を軸に受験校を選べば、少ない労力で高得点を狙えるでしょう。
むやみに受験校を増やすより、「自分の強みを活かせる大学」を見極めることが成功の近道になります。
受験する学校の数を決める際の判断ポイント

受験校数を決める際は、「学力」「日程」「費用」の3要素を軸に総合的に判断することが重要です。
まずは模試判定や過去問演習の結果をもとに、チャレンジ校・実力校・安全校の比率を調整しましょう。一般的には、チャレンジ校を1~2校、実力校を2~3校、安全校を1~2校に設定するのが目安です。
これにより、合格の可能性を確保しつつ、負担の少ない受験計画を立てられます。ただし、体力や移動距離、家庭の事情なども考慮する必要があります。無理なスケジュールを組まず、自分のペースで最大限の成果を出せるように調整しましょう。
まとめ
大学受験における受験校の数は、多いほど良いというわけではありません。平均的には3~5校を受験する受験生が多いですが、自身の学力・体力・費用面を総合的に見て判断することが大切です。
安全校・実力校・チャレンジ校のバランスを意識することで、合格のチャンスを広げつつ負担を最小限に抑えられます。
これから受験校を検討する方は、塾や予備校で相談しながら、自分に合った受験計画を立ててください。自分に合う学習環境を探している方は、「オススメ予備校一覧ページ」をぜひ参考にしてみてください。