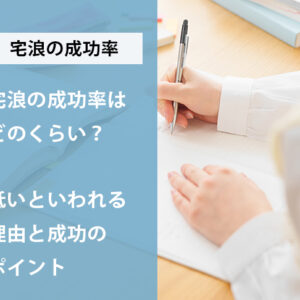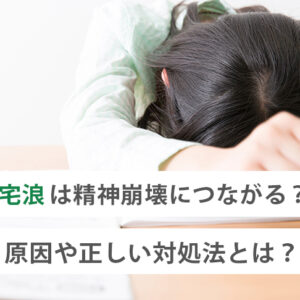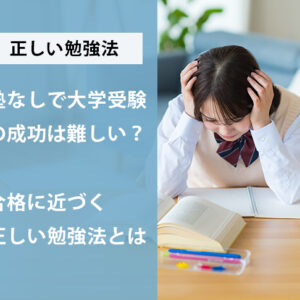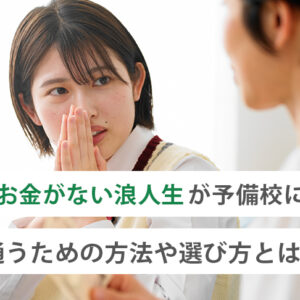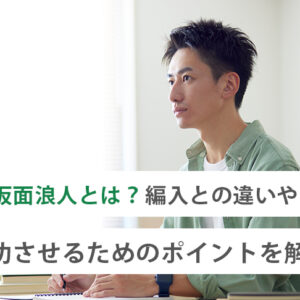受験を控える高校生は、自分の学力が平均と比べてどのくらいなのか、気になる方も多いでしょう。
この記事では、高校生の平均偏差値について紹介します。また、偏差値を上げる方法についても紹介するので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
高校生の平均偏差値はどれくらい?

高校生にとって、偏差値は自身の学力を測る重要な指標です。しかし「偏差値50が平均」と聞いても、その背景や意味を正確に理解している方は少ないかもしれません。
まずは、全国的な平均や学年ごとの傾向を踏まえ、高校生の偏差値がどのように分布しているのかを見ていきます。
全国の高校生全体で見る平均偏差値
偏差値は本来、「全体の平均を50として上下に分布させる」ように設計された指標です。正規分布に基づき、偏差値50前後に最も多くの生徒が集まり、それより上・下に向かって人数が少なくなっていきます。
ただし、実際の模試では受験者層や問題の難易度が異なるため、厳密な意味で「全国平均=偏差値50」とは限りません。例えば、難関大学を目指す層が多く受ける模試では、全体的に偏差値が高めに出る傾向があります。一方で、基礎学力を測るような模試では、偏差値の上下が小さくなることもあります。
そのため、偏差値は単体で評価するのではなく、「どの模試で出た数値か」「対象者のレベルはどのくらいか」を加味して判断することが重要です。
学年別の平均偏差値の目安
学年ごとの偏差値傾向にも違いがあります。これは高校3年間の学習を通じて、学力の向上とともに偏差値にも変化が生まれるからです。具体的には、以下のように違いがあります。
・高1:偏差値50前後
高校に入学したばかりの段階では、中学の復習内容を中心とした模試が多く、学力のばらつきが大きいです。そのため、偏差値も安定しにくく、「高い数値が出た」「思ったより低かった」と感じる生徒も多く存在します。
・高2:偏差値55前後
高校2年生になると、進路や受験に対する意識が高まる生徒が増え、模試の受験率も上昇します。それにより、学力差が少しずつ明確になっていき、偏差値にも反映されはじめます。
・高3:偏差値58~60
受験を意識する生徒が中心に模試を受けるため、平均偏差値が相対的に高くなります。高3で偏差値60を超えてくると、難関大学を狙える水準といえます。
偏差値はどのように計算されている?

偏差値は、単なる得点ではわからない「自分の位置」を相対的に示す指標です。ここからは、偏差値の基本的な計算式と具体的な求め方を紹介します。
偏差値は、以下の計算式によって求められます。
この計算式により、自分の得点が平均よりどれだけ離れているかを数値化できます。標準偏差(数値のばらつきを示す指標)を使うことで、全体分布のなかでの自分の立ち位置をより正確に把握できます。偏差値を求めるための具体的な手順は、以下のとおりです。
1.平均点を計算する
全受験者の合計得点を人数で割り、平均点を求めます。
2.偏差(得点と平均点の差)を計算する
自分の得点から平均点を引いて、どれだけ差があるかを出します。
3.偏差を2乗して全員分足し、分散を出す
各受験者の偏差の2乗をすべて足し、受験者数で割ると分散が求められます。
4.標準偏差を求める
分散の正の平方根を取ることで、標準偏差がわかります。
5.得点差÷標準偏差×10
平均点との差を標準偏差で割り、それに10をかけます。
6.最終的に+50して偏差値を出す
最後に50を足すことで、偏差値が算出されます。
このように、偏差値の計算には統計的な処理が含まれているため、単なる得点の上下だけでは見えない「全体のなかでの立ち位置」が明確になります。
偏差値における進路の違いについて

高校生の進路選択において、偏差値は重要な判断材料の一つとなります。偏差値の高低によって進学先や就職の傾向が異なるため、自身の現状を把握したうえで慎重に検討することが求められます
偏差値60以上の場合
偏差値60を超えると、全国的にも上位20%程度に入る学力水準といえます。このレベルの生徒は、難関国公立大学や難関私立大学を目指すケースが多く見られます。
例えば、東京大学や京都大学、一橋大学、東京工業大学といった難関国立大学や、早慶上智、MARCHの上位学部を志望する生徒がこの層に含まれます。学校の授業内容を超えた高度な学習が必要であり、自学自習だけでなく、塾や予備校での対策も不可欠となるケースが多いです。
また、この層の生徒は、模試や外部テストの成績も安定しており、進路への意識も高い傾向にあります。
偏差値50前後の場合
偏差値50前後は、全国的には平均的な学力層とされ、多くの高校生が該当します。この層では、中堅大学(産近甲龍・日東駒専レベル)や、地元の私立大学への進学が多い傾向があります。
また、専門学校への進学を選択する生徒も一定数存在します。将来の職業を見据えて、実践的なスキルを早めに身に付けたいという動機から、専門分野に進むケースも多いです。
学力的にはまだまだ伸びしろがあり、勉強の仕方やモチベーション次第で偏差値60台への到達も十分に可能です。
偏差値40以下の場合
偏差値40以下の層は、学力的に課題があるとされるラインです。学習習慣が身についていないケースや、受験に対する意識が低い場合も見受けられます。
この層では、進学よりも就職を選ぶ生徒が多く見られますが、一方で進学希望者も少なくありません。専門学校や一部の私立大学では、偏差値にとらわれず入学できる制度も整っているため、選択肢は限定されません。
「偏差値が低いから進学は無理」と安易に決めつけてしまうと、後悔することもあります。偏差値はあくまで一時点での指標であり、今後の努力によって変化させることが可能です。自分に合った学び方を見つけ、冷静に今後の進路を検討する姿勢が求められます。
偏差値はどのように活用すべき?

偏差値をただの数値として見るのではなく、今後の「学習や進路選び」に活かすことで、その価値は高まります。ここからは、偏差値の有効な活用法を3つの視点から解説します。
学力の現在地を客観的に把握する
先述したとおり、偏差値は「自分の成績が全体のなかでどの位置にあるか」を示す相対評価の指標です。例えば、得点が60点でも、全体の平均が40点なら偏差値は高くなります。一方で、平均点が70点なら同じ60点でも偏差値は低くなります。
したがって、偏差値を確認することで「ほかの受験者と比べて、自分の学力がどの程度か」を冷静に判断できます。さらに、模試を複数回受けてその推移を見ることで、学力の伸びや停滞も可視化され、勉強法の見直しにもつながります。
志望校を選ぶ際の判断材料にする
大学ごとに、合格者の偏差値(ボーダーライン)が設定されています。自分の偏差値と照らし合わせて、どの大学を狙えるのか、どこに届いていないのかを把握することで、現実的な志望校選びが実現可能です。
ただし、偏差値だけで大学を選ぶのは避けましょう。学びたい内容やキャンパスの雰囲気、将来の就職先など、複数の要素を考慮することが重要です。偏差値はあくまで「目安」として位置づけ、進路検討の参考情報の一つとして扱うようにしましょう。
学習計画の立案に役立てる
模試の結果では、科目別の偏差値も確認できます。この数値を活用すれば、どの教科が得意で、どの教科が苦手なのかが一目でわかります。例えば、英語の偏差値が65で数学が45であれば、数学に重点を置いた学習計画を立てるべきです。
また、志望校の偏差値と自分の現状の差を可視化することで、「あと何点必要か」「どの教科を強化すべきか」が明確になります。これにより、戦略的な学習が可能です。
偏差値を上げる方法

偏差値は、自分の現在地を知るうえで有効な指標であり、進路選びや学習計画の軸にもなります。偏差値だけですべてを決めるべきではありませんが、目標に向けて努力を積み重ねるうえで、偏差値の向上がモチベーションになることもあります。
最後に、偏差値を上げるために効果的な3つの方法を紹介します。
毎日勉強に取り組む
偏差値を上げるには、まずは「勉強時間の確保」が不可欠です。短期間で成績を大きく伸ばすことは難しいため、継続的な学習習慣が求められます。
一般的に偏差値を1上げるには、1教科あたり50時間程度の勉強が必要とされています。これはあくまで目安ですが、学習量の積み重ねが結果に直結するのは間違いありません。特に時間が限られている生徒は、「得意教科をさらに伸ばす」よりも、「苦手教科の底上げ」を優先すると、全体の偏差値が上がりやすくなります。
また、日々の学習を記録したり、タイマーを使って集中時間を意識したりするなど、学習の「質」と「継続性」を意識すると学習効果を最大化できます。
自身の学力レベルに合った勉強法を取り組む
効率的に偏差値を上げるには、「自分に合った勉強法」を見つけることが重要です。例えば、基礎がまだ定着していないのに応用問題ばかり解いても、理解が追いつかず、かえってモチベーションを下げてしまいます。
また、すでに基礎が身についている生徒が基礎問題ばかりに取り組んでいても、得点力が伸びにくくなります。
まずは模試や学校の定期テストを分析し、自分の弱点や課題を明確にしましょう。科目ごとに「いま何を優先すべきか」を把握し、それに合った教材や学習内容に取り組むことが、効率良く偏差値を上げる近道です。
予備校や塾に通う
学習計画の立て方がわからない、勉強が長続きしない、といった悩みを抱えている人は、予備校や塾に通うのがおすすめです。
予備校や塾では、受験に特化したカリキュラムや教材が提供されており、自分に合った学習プランを組むことが可能です。また、プロの講師による授業や添削、質問対応を通じて、独学では得にくい「理解の深まり」や「定着の速さ」が得られます。
特に、偏差値の推移を見ながら戦略的に学習したい生徒には、予備校での「クラス分け」や「志望校別対策コース」がおすすめです。学力に応じたグループで学ぶことが刺激となり、モチベーション維持にもつながるでしょう。
まとめ
高校生の偏差値は、基本的には全国平均で50を基準としていますが、模試の種類や学年によってばらつきがあります。高1では偏差値50前後、高2で55前後、高3になると58~60程度が平均的とされています。
偏差値は学力の「相対的な現在地」を示すものであり、進路選び・学習計画・モチベーションの管理において役立つ指標です。ただし、偏差値だけで志望校や将来の選択肢を決めるのではなく、興味や適性、学校の教育方針なども併せて検討することが大切です。
もし、偏差値を上げたいのであれば、まずは毎日の学習習慣を見直し、自分に合った勉強法を取り入れることからはじめましょう。必要であれば、塾や予備校を活用するのも効果的です。学習環境を整えることで、目標への距離は確実に縮まります。これからの進路選びに向けて、自分の学力を冷静に見つめ、着実な一歩を踏み出していきましょう。
塾・予備校を探している高校生の方は、「オススメ予備校一覧ページ」もぜひチェックしてみてください。