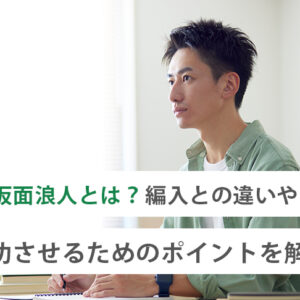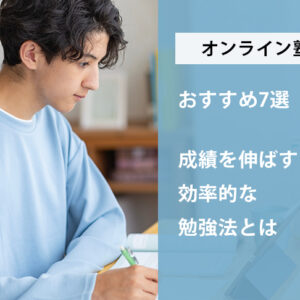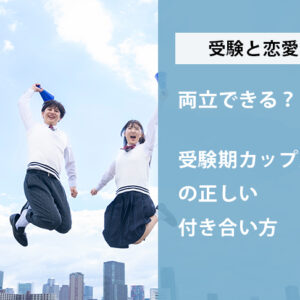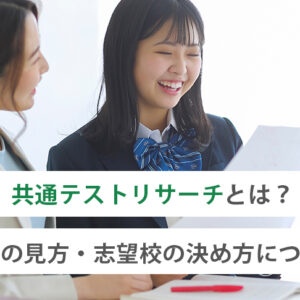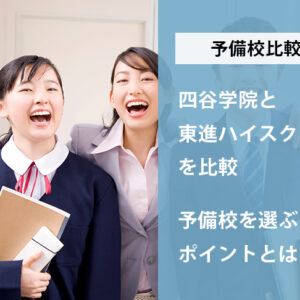志望校を巡って親と意見が合わず、どう説得すればよいか悩む方もいるでしょう。しかし、親の不安に配慮しつつ、模試結果や学費の情報を整理して丁寧に説明すれば、理解を得られる可能性が高まります。
また、冷却期間をおいたり、第三者の力を借りたりすることも有効です。この記事では、志望校を親に納得してもらうための準備や話し方を具体的に紹介します。親の説得に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ親は志望校を反対するのか?

親が志望校に反対する理由として多いのは、学費・将来性・偏差値といった点への懸念です。
まず学費は、進学にかかる費用が家計に大きな負担となることがあります。私立大学や遠方の大学は、授業料だけでなく生活費も加わり、親の不安を招く要因となるでしょう。
次に将来性については、志望校の学部や専攻が卒業後の就職・キャリアにどれほどつながるかを心配しています。また、志望校の偏差値が本人の学力に合っていない場合も、親の懸念点となりやすいでしょう。
親の反対には、単なる否定ではなく「子どもの将来」を思う気持ちが込められています。そのため、否定されても感情的にならず、費用の見通しや将来のビジョンをしっかり伝えることが大切です。
親を説得する前に明確にすべきこと

親を説得するには、志望校への思いを明確にすることが大切です。本当にその大学に行きたいのか、なぜ必要なのかを整理することで、納得してもらいやすくなるでしょう。
「本当に行きたいのか?」を自分に問い直す
まず、「自分は本当にその大学に行きたいのか」を改めて考えましょう。志望校を選ぶ際、偏差値や大学のイメージだけで決めていると、親を納得させられない可能性が高いです。
また、志望校に合格するためにどれだけの努力をしているかも重要なポイントです。相応の努力をしていることが伝われば、親から納得してもらえる可能性が高まります。
志望校が必要な理由を明確にする
親を説得するうえで、「なぜその志望校でなければならないのか」を明確に伝えることが大切です。そのためには、志望校で学びたい学問や分野について、具体的に調べておきましょう。
たとえば、その大学特有のカリキュラムや研究施設、教授陣など、自分の学びたい内容とどのように結びついているのかを整理しておくと説得力が増します。
また、卒業後の進路や将来の目標と、どのように関係しているかを示すのも効果的な方法です。「将来〇〇の仕事をしたいから、この学部で△△を学ぶ必要がある」といった説明を行えば、親が抱える不安の軽減につながります。
さらに、OBやOGの進路や活躍を調べることで、自分がどんな将来を描いているのかを具体的に伝えられます。根拠を持って志望校を語る姿勢こそ、親からの信頼を得るための第一歩となるでしょう。
親を説得するための準備

親を納得させるには、具体的な根拠が必要です。説得する前に、学費や模試結果などのデータを揃えておくようにしましょう。
以下では、親を説得するための準備について詳しく紹介します。
学費のシミュレーションや奨学金の情報を整理する
志望校にかかる費用を具体的に把握することは、親を説得するうえで重要な要素です。まず、入学金や授業料、施設費などを含めた初年度の学費、そして4年間でかかる総額を計算しておきましょう。
そのうえで、奨学金や教育ローンを利用できるかを事前に調べておくことも有効です。たとえば、給付型や貸与型など、どの制度が利用できそうかを具体的に説明できれば、親の不安も和らぎます。
また、親の経済的な負担を軽減するために、自分がどの程度のアルバイトをどのくらいの時間できるか、といった見通しも合わせて伝えると、現実的なプランとして受け入れられやすくなります。
大学によっては、学費免除や減額制度を活用できる可能性があるため、これらの情報も調べておくとよいでしょう。
大学の資料や模試の結果を揃えて説明する
説得力のある説明を行うには、大学に関する具体的な資料や模試結果を用意しておくことが大切です。志望校のパンフレットや公式サイト、オープンキャンパスの体験内容などを基に、どのようなことを学べるのかを具体的に説明しましょう。
親としては、大学の雰囲気や学部の特色がわかる情報があると、安心材料となるでしょう。また、模試の成績や判定を見せることで、志望校へ合格する可能性を客観的に示すことができます。仮に判定が厳しい場合でも、これからの学習計画や成績の推移を見せれば、努力次第で届くという意志を伝えられるでしょう。
さらに、志望学部の強みや卒業後の進路実績なども整理して伝えると、卒業後に子どもがどのような道に進むのかをイメージしやすくなります。
先生や塾のアドバイスをもらう
自分だけで親を説得するのが難しい場合は、学校や塾の先生の力を借りるのも有効な方法です。日頃の学習状況や志望校への適性をよく理解している先生に、親を説得する際のポイントを相談してみましょう。
先生から合格実績に基づいたアドバイスや、現時点での学力に合った勉強計画などを示してもらうことで、より現実的な説得材料が整います。また、先生が受験の展望や課題を説明してくれると、第三者からの客観的な意見として受け入れやすいでしょう。
塾の進路指導担当者や学校の進路指導室に相談すれば、資料や過去の合格者の情報を得られる可能性もあります。
親を説得するための伝え方

親を説得する際は、自分の熱意だけで押し通すのではなく、親の不安に寄り添いながら冷静に伝える姿勢が大切です。以下では、納得してもらいやすい説得の仕方について紹介します。
親の不安に寄り添う
先述した通り、親が志望校に反対する背景には、学費や将来性、学力への不安など、子どもを思うからこその心配があります。その気持ちを無視して一方的に主張しても、対立が深まるだけです。まずは親の話に最後までしっかりと耳を傾ける姿勢を持ちましょう。
「どうして反対なのか」を冷静に尋ね、その不安に対して一つひとつ具体的な解決策を提示するのが大切です。たとえば「学費が心配」であれば、奨学金の活用やアルバイトを行うことを伝えるようにしましょう。一方で、「将来が不安」であれば、卒業後の進路やキャリアの情報を共有することで、親に納得してもらいやすくなります。
また、話し合いは一度で決着させようとせず、複数回に分けてじっくり時間をかけて進めるのもひとつの方法です。感情的なぶつかり合いを避け、落ち着いた雰囲気で誠意を持って話すことで、親からの信頼を得やすくなるでしょう。
「〇〇大学に行きたい!」ではなく「〇〇大学で△△を学びたい」と伝える
親を納得させるには、「〇〇大学に行きたい」といった感情的な表現ではなく、「〇〇大学で△△を学びたい」という具体的な目的を示すことが重要です。「行きたい」という気持ちは理解できますが、それだけでは説得力に欠け、親は「雰囲気だけで選んでいるのではないか」と不安に感じてしまいます。
そこで、「この大学の◯◯学部では××の研究に力を入れていて、自分の関心と一致している」「将来は□□の仕事に就きたいから、この分野の学びが欠かせない」といった具合に、学びたい内容と将来の目標を明確に関連づけて説明することが大切です。
大学で何を学び、どのように成長し、それが将来にどうつながるのかまで語れるようになれば、親も子どもの本気度をより深く理解できるようになります。目的や目標を明確にすることで、志望校への進学が単なる憧れではないことをしっかりと伝えられるでしょう。
もし親が納得しなかった場合はどうする?

どれだけ丁寧に説明しても、すぐに親が納得するとは限りません。そのような場合に、感情的になっては逆効果となります。冷却期間を設けたり、第三者の力を借りたりするようにしましょう。
一度冷却期間をおいて再度話し合う
親との話し合いで納得を得られなかった場合、すぐに再度説得しようとするのは逆効果です。お互いが感情的になっている状態では、冷静な対話は望めません。そのような場合は一度距離をおき、冷却期間を設けるようにしましょう。この期間を活用して、自分の志望理由や進路の情報を改めて整理し、説明の準備を整えるようにしてください。
また、親の立場になって再度考えてみることで、別の伝え方や新たな視点が見つかるかもしれません。ほかの大学への入学も考慮したうえで一度見直した結果、第一志望の大学に進みたいという結論に至れば、親にも納得してもらえる可能性が高まります。時間をかけて話すことは決して妥協ではなく、より深い理解を築くための大切なプロセスです。焦らず、誠実に向き合い続ける姿勢こそが、最終的に親の理解を得るための鍵となるでしょう。
家族以外の第三者(先生・塾の講師など)を交えて相談する
自分だけで親を説得するのが難しいと感じたときは、家族以外の信頼できる第三者に相談するのも有効な方法です。学校の先生や塾の講師は、進路や大学の実情に詳しく、親が抱える不安に対して客観的な説明をしてくれるでしょう。親としても、身近な大人の意見であれば、子どもの主張だけを聞くよりも受け入れやすいものです。
また、同じように親の反対を経験し、乗り越えた先輩や友人の体験談を聞かせるのも効果的です。一人で悩まず、周囲のサポートを得ながら、前向きに親との対話を続けていきましょう。
まとめ
親に志望校を反対されたときは、なぜ不安を感じているのか、その理由を理解することが大切です。そのうえで、自分の意志や将来のビジョンを明確にし、学費や模試結果などの必要な情報を整理し、丁寧に説明することを心がけましょう。感情的にならず誠実に話すことが、説得への第一歩です。
それでも親が納得しない場合は、先生や塾の講師など、第三者の力を借りることをおすすめします。塾や予備校からのアドバイスが必要な方はぜひ「オススメ予備校一覧ページ」をぜひご覧ください。