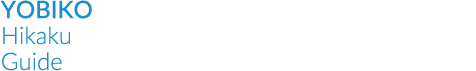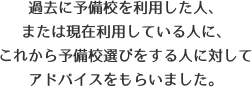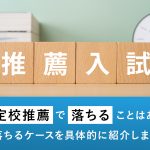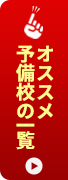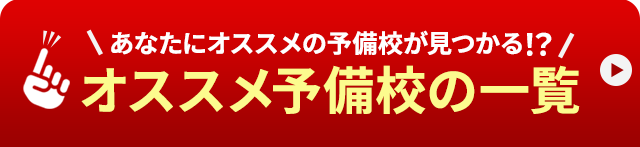大学受験の小論文対策はいつから?何する?おすすめ勉強法や参考書・塾・アプリを紹介

大学受験で小論文がある場合には、事前対策が必要です。
しかし小論文の場合は単に暗記で対応するのではなく、着実に練習を積み重ねる必要があるため、どこから手をつけたらいいか分かりづらいこともあるでしょう。
そこで本記事では、大学受験の小論文対策はいつから始めれば良いのか、おすすめの勉強法、おすすめの参考書・アプリ・塾についてまとめました。
結論、試験の1年前から余裕を持って小論文対策を始めるのがベストです。
記事を最後までチェックすれば、大学受験の小論文対策に関する情報がひと通り手に入りますよ。
大学受験の小論文対策はいつから始めるべき?
大学受験の小論文対策は、早く始めるに越したことはありません。理想は1年前からコツコツと対策を進めることです。
小論文の試験は、学校推薦型選抜・総合型選抜のみならず、国公立大学の後期試験やAO試験などでも課されることがあります。
小論文が書ければ「説得力のある志望理由書が書ける」など、別の場面でも大いに役立ちます。
小論文が課される大学と選抜方式の例
ここでは、小論文が課される大学と選抜方式の一例を紹介します。なお、すべての学部学科に小論文が課されているわけではないため、詳しくは各大学の募集要項をご確認ください。
- 北海道大学:一般後期、総合
- 筑波大学:一般、学校推薦
- 東北大学:AO
- 東京大学:学校推薦
- お茶の水女子大学:一般後期
- 大阪大学:学校推薦、総合
- 京都大学:一般後期、特色入試
- 九州大学:一般、総合
- 一橋大学:学校推薦
- 慶應義塾大学:一般、総合
- 上智大学:一般、公募推薦
- 早稲田大学:一般、グローバル、自己推薦
小論文対策は2ヵ月以上必要
受験に小論文がある場合は、事前の対策が必要です。まず、出題テーマの傾向や論文の書き方の基本を確認しておきましょう。
勉強にかかる時間は最短でも2ヵ月程度と言われています。
小論文の出来不出来は個人差が大きく、文章を書き慣れていない人であれば、1年前から準備する必要があるかもしれません。志望校が途中で変わる可能性も考慮して、できる限り早めに対策を始めましょう。
これらの状況を踏まえると、本格的に小論文対策を始める時期は、受験する選抜方式により、以下の表のように整理できます。
単純に、「受験時期から逆算して2ヵ月前から始めればよい」とはならないことに注意が必要です。
選抜方式 | 受験時期 | 小論文対策の開始タイミング |
学校推薦型・総合型 | 9~11月ごろ | 4月ごろ |
私立大学一般 | 1月下旬 | 前年の9~10月ごろ |
国公立大学一般 | 2月下旬~3月中旬 | 前年の5月ごろ(後期選抜を受験する場合は、前期試験終了後からも可能) |
それぞれのポイントは、以下の通りです。
①学校推薦型選抜・総合型選抜の場合
難関校の学校推薦・総合型選抜を目指す場合は、高校の成績も一定以上の実績が必要です。
各方式の選抜試験が行われる2ヵ月前は、単純計算すると7〜9月ですが、夏から秋は学校の行事や講習、課外活動、定期試験、模擬試験などやるべきことが重なりがちです。
そのため、夏から小論文対策を始めるよりは、高校3年生の4月ごろから着手するのがおすすめです。
②私立大学一般選抜の場合
私立大学を第一志望としている場合は、勉強する科目も絞られます。共通テストの受験も考慮して9〜10月ごろから対策を行いましょう。
③国公立大学一般選抜の場合
国公立大学を受験する場合は、共通テストの受験対策が本格化する秋よりも前に終わらせておくのがおすすめです。
小論文対策は、授業の履修範囲の影響をあまり受けないため、5月ごろから着手し始めて、夏までに一通りの対策ができていれば、共通テストや受験の2次試験対策に注力しやすくなります。
また、後期選抜を受験する場合は、国公立大学の前期試験が終わったあとに小論文を書く練習を行うことも可能です。
大学受験の小論文対策は1ヶ月でもできる?
結論、環境によっては1ヶ月でも大学受験の小論文対策は可能です。
しかしその場合、勉強時間を全て小論文対策に費やせることが条件となります。また塾・予備校に通うなどして、常に小論文を添削してもらえる環境にいることも条件です。
試験本番まで1ヶ月を切った状態でこの記事を見ているのであれば、仕方がありません。今すぐ塾や予備校に問い合わせてみることをおすすめします。
オススメ予備校一覧ページをチェックしてみてください。
試験1ヶ月前になって焦らないためにも、今のうちから小論文対策は始めておきましょう。
十分な期間があれば、毎日数時間を小論文対策に費やす必要はありません。月に数日の学習でも、十分対策は間に合います。
大学受験の小論文対策では何をする?おすすめの勉強法5選

大学受験の小論文対策におすすめの勉強法は以下の5つです。
- 一般的な小論文の出題形式を知る
- 小論文の失敗傾向を知る
- 志望校の小論文の出題情報を集める
- 何本も論文を書く
- 個別に添削指導を受ける
それぞれ詳しく見てみましょう。
一般的な小論文の出題形式を知る
小論文の出題形式は、大学や学問系統で異なります。まずは小論文にどのような出題形式があるのかを知りましょう。
小論文の出題形式を大きく分類すると以下のとおりです。
小論文の出題形式 | 医・歯・薬 | 保健・看護 | 理・工 | 農林水産 | 社会・情報 | 国際社会・国際文化 | 生活・環境・福祉・地域 | 人文 | 教育 | その他学部 |
指定テーマについて論じる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本語の課題文に関して論じる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英語の課題文に関して論じる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
図表・グラフから必要な情報を解析して論じる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日本語や英語の課題文から理数系の計算問題につなげて論じる | ○ | ○ | ||||||||
学部や学科への志望動機などを論じる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
学部によっては、課題文自体が英語の場合があります。
また、医・薬系や理・工系では、日本語や英語の文章から理数系の計算問題につなげて論じる小論文があるため、読解力の向上など事前に十分な対策が欠かせません。
小論文の失敗傾向を知る
失敗傾向を把握しておくことで、正しく小論文を書けるようになります。ここでは、以下4つの小論文の失敗例について紹介します。
- 感想を書いてしまう
- 文字数の過不足がある
- 設問に答えられていない
- 解答用紙の使い方に誤りがある
それぞれ詳しく見てみましょう。
感想を書いてしまう
作文や感想文では、好き嫌いなどある事柄に関して自分の主観や個人的な考え方などを率直に述べてもかまいません。
しかし小論文の場合は、自分の感覚だけに頼った発言は厳禁です。小論文では、ある問題の理由や根拠を明示して論理性を保ち、客観的事実に基づいて問題の対策案や価値、可能性、重要性などを述べることが求められます。
文字数の過不足がある
文字数に制限がある場合、制限文字数を1文字でも超えたり、逆に文章が短すぎたりすれば減点の対象となります。
小論文は、指定文字数の8〜9割を埋める必要があるため、800文字の指定であれば640〜720文字以上は書かなければなりません。
文字数を見て「どのくらいの文章量で論理を展開すべきか」についてイメージできるように、練習しておきましょう。
設問に答えられていない
設問に正しく答えられていない小論文は、減点されます。以下、設問に答えられていない小論文の例です。
問「社会問題にどう取り組むべきか」 誤回答例「○○という課題がある」「人口が増えないと解決できない」 |
問「人間における愛情とは何か」 誤回答例「自分は愛情を○○と捉える」「(理由を示さずに)愛情は子どもの成長に重要だ」 |
問題や事実を列挙しただけで終わらないように、最初に結論を示しておくことが大切です。
PREP法など小論文向けのフレームワークを理解しておくと役立ちます。時間配分に注意して、不必要な文章をそぎ論旨をまとめてから回答を作成しましょう。
課題文がある場合は自分の立場を明確にしたり、資料を読みとる小論文であれば資料の特徴的な箇所に注目したりするなど、出題傾向を踏まえて小論文を書く練習を重ねることが大切です。
解答用紙の使い方に誤りがある
小論文の場合、読みやすさだけではなく構成も意識しましょう。
序論・本論・結論の3段構成で、文体は「だ・である」調とするのが基本です。文章の表現方法や構成の仕方、文体などにも一定のルールがあります。題名や段落の書き始め方、句読点(。、)やかっこ(「」『』)などの使い方も確認しておきましょう。
志望校の小論文の出題情報を集める
小論文対策は、受験する学部に関わるテーマや時事問題が選定される傾向があります。
最近のニュースや企業の報道、論文の発表など最新情報はもちろん、専攻に関わる話題や、自分が将来学びたいことなど幅広い情報収集が必要です。
それぞれの学問系統で、よく出されるテーマは、以下のようなものがあります。
学問系統 | 小論文の出題テーマ例 |
医・歯・薬 | 医療、生命科学 |
保健・看護 | 医療・健康、コミュニケーション、子ども、高齢者 |
理・工 | 自然現象、技術 |
農林水産 | 食、環境、農業や水産業の活性化、生物多様性 |
法・政治 | 政治、民主主義、法制度、人口減や高齢化を踏まえた地方創生 |
商・経済 | 情報化、教育、少子高齢社会、財政、経済、企業経営 |
社会・情報 | 情報社会、エネルギー・環境、少子高齢化 |
国際社会・国際文化 | 文化、言語、国際関係、異文化交流 |
生活・環境・福祉・地域 | 環境、少子高齢社会、衣食住 |
人文 | 人間、文化、言語、知 |
教育 | 教育者として将来の展望、専門教科に関わる学問 |
何本も論文を書く
どのような小論文を作成すべきか知っていても、実際に書いてみないと論文は上達しません。
時間が許す限り、できるだけたくさんの小論文を書いてみましょう。
作成したあとは、翌日などに一度読み直して文章を練りこむのも有効です。また1つのテーマであっても、複数の文章を書いたり推敲し直したりすることで実力がより高められていきます。
個別に添削指導を受ける
上述した通り、小論文対策はやるべきことが多岐にわたるため、小論文のプロに添削指導してもらうことも検討しておきましょう。
自分の書いた文書を添削してもらうと、意外な視点や客観的にどう見えるのかなどがわかります。
小論文の個別指導であれば、志望学部により効率よい情報収集ができるうえ、書いた文章をその場で指導してもらえます。
自分が納得するまで推敲を重ねることで、本番の試験では、確たる主義主張が展開できるようになるでしょう。
小論文を添削してもらいたい方におすすめの塾・予備校については、後ほど詳しく紹介します。
大学受験の小論文対策におすすめの本・参考書2選
大学受験の小論文対策におすすめの本・参考書は以下の2冊です。
- 7日間で合格する小論文-読み方&書き方を完全マスター!
- 何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55
参考書は、短期間で小論文対策の要点を掴むのに役立ちます。それぞれ詳しく見てみましょう。
7日間で合格する小論文-読み方&書き方を完全マスター!
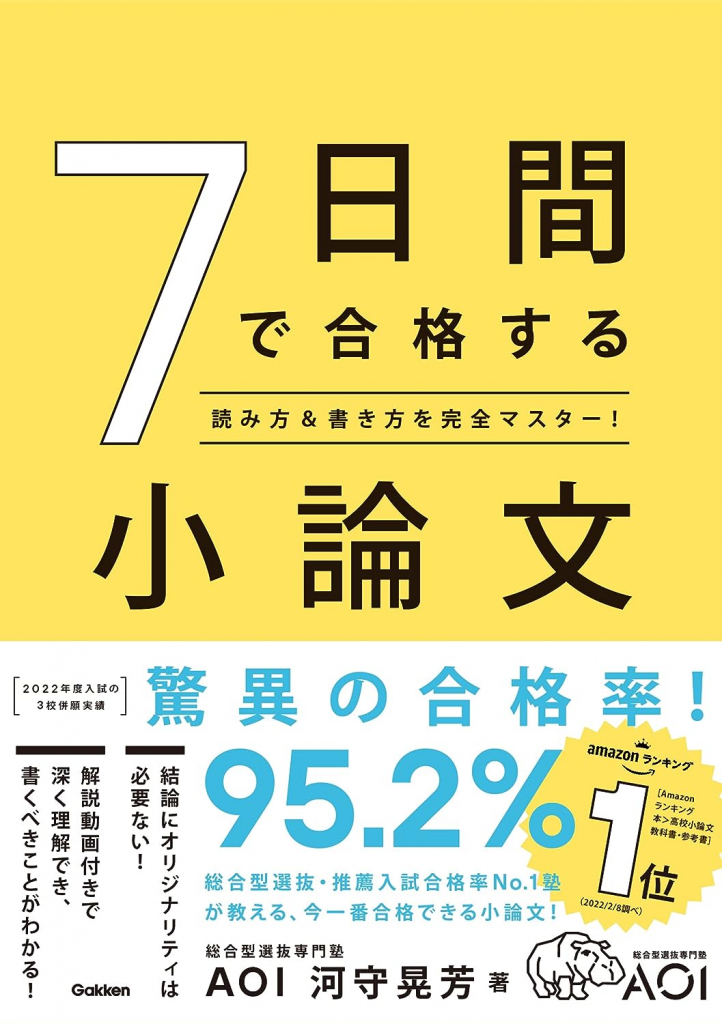
価格:1,540円
「7日間で合格する小論文-読み方&書き方を完全マスター!」は、タイトルの通り7日間で小論文に必要なことを最低限学べる参考書です。
減点ポイントや加点ポイントに加えて、練習問題や解説動画もついています。
練習問題の量がやや少なめで、小論文対策に不十分ではありますが、短期間で小論文対策をしたい方にはぴったりの参考書です。
何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55
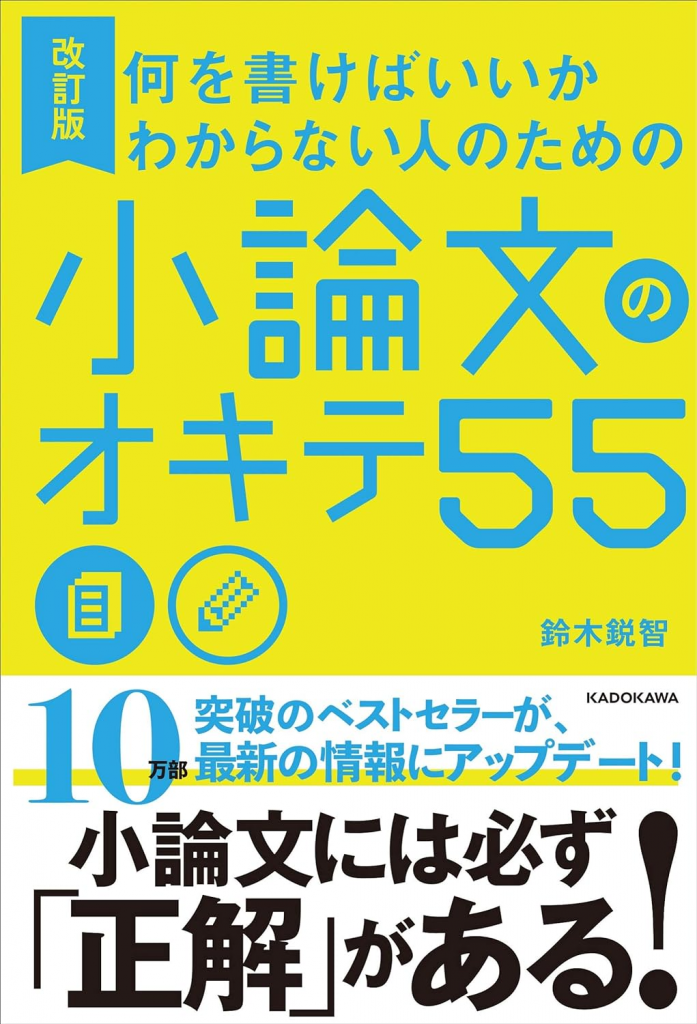
価格:1,100円
「何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55」では、小論文の書き方について、55のセクションに分けて解説をしています。
よって一歩ずつ着実に、小論文の対策ができます。「毎日⚪️セクションずつ学習する」のような勉強方法もおすすめです。
本書の51セクション目には、「過去問を解く」というセクションがあります。
本書を使えば「何となくルールは分かったけどこの後どうすれば良いんだろう」と不安を抱くことはありません。
小論文対策が万全と言えるまでに何をすれば良いのかが明確に分かります。
大学受験の小論文対策におすすめのアプリ2選
大学受験の小論文対策におすすめのアプリは以下の2つです。
- Clearnote
- i-暗記シート
それぞれ詳しく見てみましょう。
Clearnote
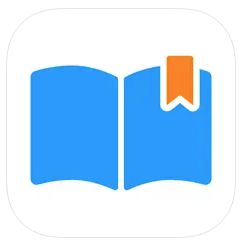
「Clearnote」は、ノートの共有アプリです。大学受験をしている方がどんなノートを取っているのかを閲覧できます。
アプリ内で「小論文」と検索をすれば、小論文対策をしている人がどんなノートを取っているのかが分かり、参考になります。
「小論文の対策、他の受験生はどう進めているんだろう?」と気になった際は、「Clearnote」を使ってみてください。
i-暗記シート
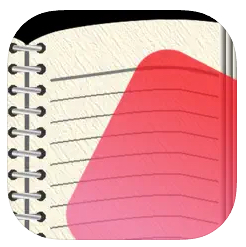
App Store / GooglePlay(非対応)
「i-暗記シート」は、アップロードした画像データをもとに、赤シート・暗記シートを作成できるアプリです。
ノートや参考書を、暗記シート化できます。例えば、覚えておきたい小論文のルールをまとめた紙を暗記シート化するなどして活用しましょう。
「i-暗記シート」は小論文のみならず他の教科の受験対策にも役立つので、インストールしておいて損はありません。
大学受験の小論文対策におすすめの塾・予備校2選
大学受験の小論文対策におすすめの塾・予備校は以下の2校です。
- 四谷学院
- 坪田塾
それぞれ詳しく見てみましょう。
四谷学院
四谷学院は「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」のダブル教育によって大学受験をサポートする予備校です。
四谷学院では、通常教科の授業に加えて、1対1での小論文の添削指導も実施しています。また年間を通じて小論文対策ができる講座も実施しています。
よって小論文について個別で学びたい方にも集団で学びたい方にもぴったりです。
四谷学院の個別相談会にて「小論文の対策をしたい」と伝えてみましょう。
坪田塾
坪田塾は、「ビリギャル」のモデルとなった個別指導塾です。坪田塾でも四谷学院と同じように、個別での小論文対策が可能です。
ビリギャルは、慶應義塾大学のSFCに合格をしています。そしてSFCを受験する際のビリギャルの受験科目は、英語と小論文の2つです。
こういった経緯からも、坪田塾は小論文対策にぴったりな塾であると言えます。
坪田塾の口コミについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:坪田塾の口コミが最悪って本当?評判や合格実績、料金などを徹底調査
大学受験の小論文は志望校別の個別対策が効果的
大学受験の小論文対策はいつから始めれば良いのか、おすすめの勉強法、おすすめの参考書・アプリ・塾について解説しました。
大学入試の小論文では、傾向分析と情報収集、小論文を書く練習の積み重ねが求められます。
大学受験の小論文対策は、できれば試験の1年前から、すでに1年を切っている場合は今すぐにでも始めたいところです。
他の教科との学習バランスを考えて、効率よく学習を進めるためには、小論文対策として個別指導を活用するのも一案です。
小論文対策のための塾・予備校を探したいのであれば、ぜひオススメ予備校一覧ページをチェックしてみてください。