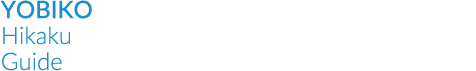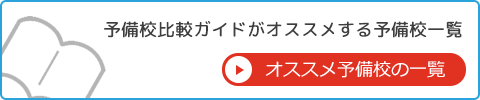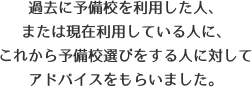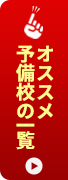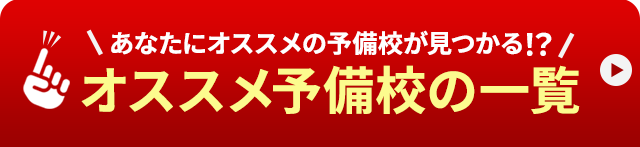E判定でも合格可能!大学受験模試で合否判定より重視すべきポイント

大学受験生の多くは、すでに複数の大学受験模試を受けた経験があるかもしれません。なかには、模試の合否判定に一喜一憂している人もいるのではないでしょうか?しかし、合否判定がEで志望校に合格する人もいるので、最後まで志望校をあきらめる必要はありません。むしろ、模試の結果で重視すべきポイントは、合否判定以外のところにあります。
重視ポイントを十分にチェックしたうえで現状の把握や改善などを行わないと、模試を受けた意味が薄れてしまいかねません。同時に、入試本番に合格ラインを超える得点を獲得できるだけの実力をつけることも難しいでしょう。とはいえ、合否判定にも意味がありますので、それについてもよく理解し、適切な形で活用することが大切です。
本記事では、まず大学受験模試の合否判定の仕組みについて解説します。あわせて、模試結果の合否判定で重視したい2つのポイントや、最後まで志望校をあきらめなくてよい理由についてもお伝えします。
大学受験模試の「合否判定」とは?
最初に、受験生の多くが気にする大学受験模試の「合否判定」について簡単に説明します。
合否判定は「志望校に合格する可能性」を示す数値
大学受験模試の合格判定は、模試を受けた時点の「志望校に合格する可能性」を示す数値です。その指標となるのが模試の偏差値と各大学の受験偏差値です。合否判定の設定では、過去の大学受験データをもとに各大学の合格ラインとなる偏差値を算出。その偏差値と模試受験者の偏差値を照らし合わせる形で、各受験生の合格可能性をパーセンテージで示します。
一般的な大学受験模試の合否判定基準は5段階
一般的な大学受験模試の合格ライン、つまり合否を判定する基準は5段階です。例えば、偏差値50の受験生が80%合格している大学に合格する可能性は80%(A判定)です。また、偏差値50の合格者が20%以下の大学なら、偏差値50の人がその大学に合格する可能性は20%(E判定)となります。ただ、模試の実施団体によっては別の基準で合否判定を行う場合もあるため、注意が必要です。
さらに、模試で合否判定がAでも入試の結果が不合格になる場合もあるので、模試の合否判定が絶対ではありません。
大学受験模試の合否判定はあくまでも「目安」

先述した理由から、合否判定は単なる目安と考えたほうがよいでしょう。その理由は、3つあります。
1.合否判定=本番の結果ではない
当然、模試の合否判定は受験本番の結果ではありません。志望校の合否判定がAでも入試の成績が悪くて不合格になる人、逆に志望校の合否判定がEでも、入試で良い成績を取って合格する人はいます。
2.合否判定ランクの分布は均一ではない
合否判定ランクの分布は、均一ではありません。なぜなら、模試によって受験者数や受験者のレベルが異なるからです。例えば、レベルが高い受験生が多い模試は平均点が高くなり、合格判定のランクは低くなる傾向です。その場合は、E判定など一番低いランクに多くの受験生が入ってしまう可能性もあるでしょう。
一方、レベルが低い受験生が多い模試では逆の現象が起こる可能性があります。つまり、合否判定ランクは模試を受ける受験生のレベルによって大きく異なる場合があるのです。
3.合否判定は変化する可能性が高い
受験生の成績は、受験本番まで変化し続け、それと連動するように合否判定も変化し続ける可能性が高いです。最後に受けた模試のあとに、成績が大きく上がることもあります。入試本番では、大学が設定する合格ラインを超えれば合格できます。つまり、仮に最後に受けた模試の合否判定がEでも、その後大きく成績が上がれば合格できる可能性は高いということです。
もちろん、合格判定は模試を受験した時点の実力ですから、合否判定のランクが低ければ弱点をつぶして自らの実力を上げていくことが求められます。その場合は、「今はまだ合格ラインに達していないだけ」と考え、本番に向けて淡々と弱点をつぶして学力を上げていくことが大切です。
大学受験模試に臨む際のポイント
受験模試に臨む際には、冷静な気持ちで取り組み、自信を持ちながら学びの機会と捉えることが大切です。その為のポイントを紹介します。
焦りを抑える
受験模試は本番試験のシミュレーションであり、結果が自身の現在の受験力を反映します。しかし、焦って取り組むことは冷静な判断や効果的な解答に妨げとなります。冷静に問題に取り組み、一つずつ解いていくことが大切です。
自信を持つ
受験模試に臨む際には、自分の過去の努力や学習の成果に自信を持ちましょう。自信があるときっかけやモチベーションを高めることができ、より良い結果を出すことができます。
学びの機会と捉える
受験模試は自身の強みや弱点を知る機会でもあります。結果が良くなかった場合でも、それを学びとして捉え、弱点を克服するための対策を立てましょう。挫折せずに前向きな姿勢を持ち続けることが重要です。
練習と成長の一環と捉える
受験模試は、本番試験に向けた練習の一環です。失敗や課題があっても、それを成長の機会ととらえ、次に活かすことが大切です。受験の道は短期間の一時的な取り組みではなく、長期的な成長と準備が必要です。
結果を客観的に受け止める
受験模試の結果は客観的なデータです。結果が良かった場合は喜び、努力の報酬として受け止めましょう。逆に結果が悪かった場合でも、それを自身の課題として受け止め、改善点を見つけることが重要です。
大学受験模試の結果で合否判定より重視すべきポイント
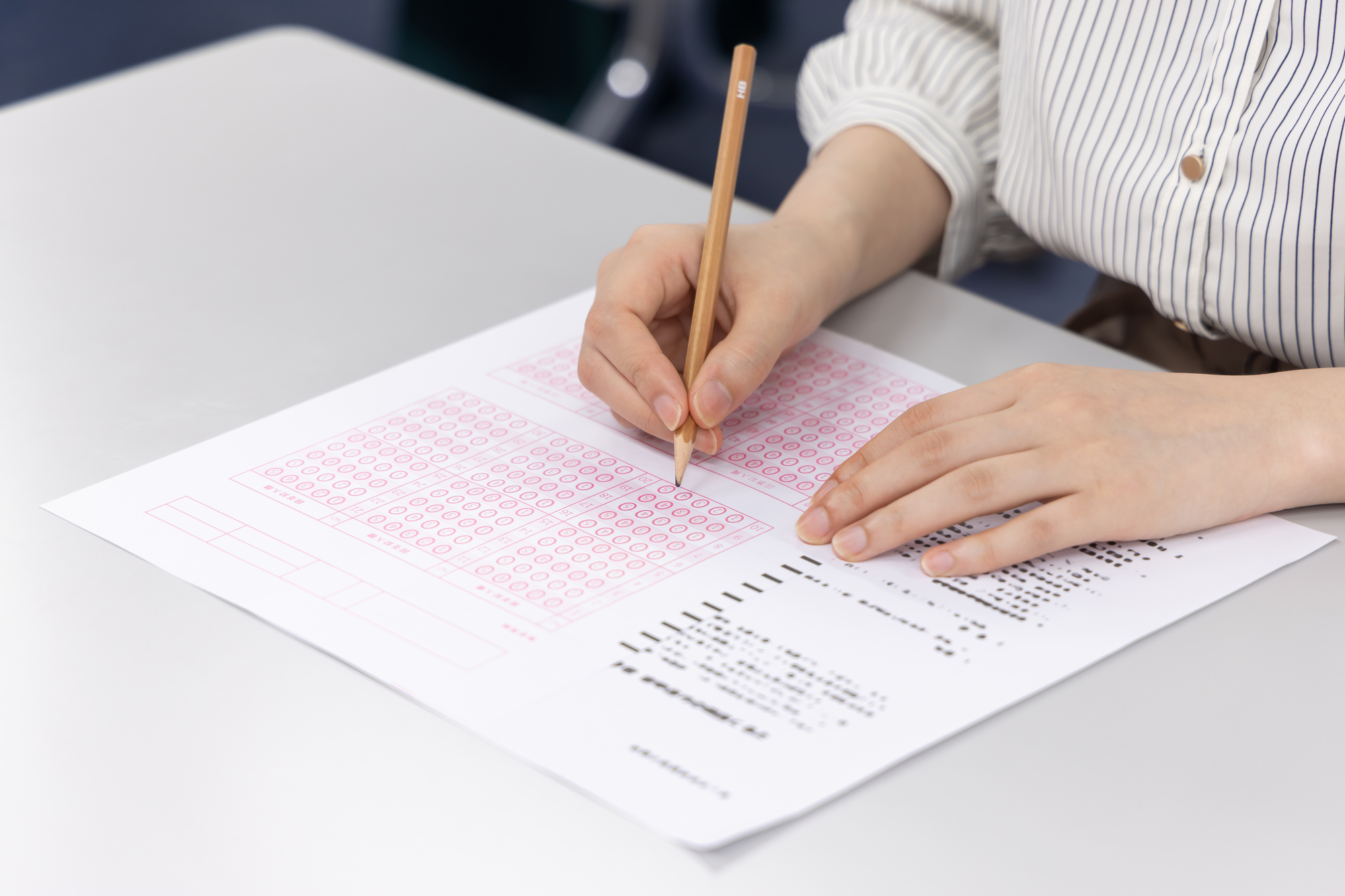
大学受験模試で合否判定を気にしてしまう受験生は多いのではないでしょうか。しかし、実は合否判定よりも重視したいポイントが「現状の把握」です。ここでいう「現状の把握」とは、「模試受験時点の自分の実力や弱点などを正しく把握すること」ですす。実施団体がデータ化した模試の採点結果は、自分の弱点が簡単にわかるようにできています。
弱点を一つずつ克服していくことが志望校合格につながっていくため、採点結果から浮き彫りになる弱点のチェックは不可欠です。特に、以下の2つは弱点をチェックするうえで最も重視すべきポイントとなります。
1.間違いが多かった単元
「間違いが多かった単元=自分の弱点」です。間違いが多かった単元は、理解しているつもりでも実際には理解度が足りないまま放置されている状態ともいえるでしょう。その状態のまま受験本番に臨めば、また同じところを間違えて受験に失敗する可能性が高くなります。
失敗を回避するためにも、採点結果を見て「自分が苦手な単元」「間違えやすいところ」などの弱点をあぶり出し、一つずつ克服していくことが重要です。模試の結果が戻ってくるたびに反復していけば、以後の模試で失点を大幅に減らせるかもしれません。学力が着実に上がっていけば、志望校の合格を勝ち取る可能性を高めることができます。
2.全体の正答率が高いのに自分は間違えた問題
全体の正答率が高いにもかかわらず間違えた問題にも注意が必要です。主な原因としては、以下の2つが考えられます。
・実は自分の弱点だった
・問題の読み違えなどのケアレスミスが発生している
間違えたところが自分の弱点とわかった場合は、苦手な単元の理解を深めるなどの方法で弱点を克服していきます。一方、ケアレスミスの場合は、不注意が原因で起こることが多い傾向です。例えば、「問題を解く時間の配分を間違えた」などの理由から動揺して不注意になり、ケアレスミスが出てしまいます。緊張しやすい人は、動揺してケアレスミスが出る可能性が高いでしょう。
例えば「自分がどんな状況で不注意になりやすいか」という点を事前に確認し、試験までに対策を講じておくと安心です。具体的には、以下の3つのような対策が有効です。
・あらかじめ苦手な単元などの弱点を克服しておく
・回答時間の配分をある程度考えておく
・試験会場の事前リサーチを行う
これらの対策は、入試本番でも応用できるので、ぜひ覚えておいてください。
自分の弱点を見つけるための手順と対処法
弱点を見つけるための分析と、それに対する対処法の検討は、自己評価と目標達成に欠かせません。弱点を明確にするための手順と対策を紹介します。
テスト結果の分析
科目ごとのスコアを確認しましょう。どの科目で得点が低かったか、どの分野や範囲で問題が多かったかを把握します。 間違えた問題を再度解いて、誤った理解や解答方法を特定しましょう。間違いのパターンや共通のミスを見つけることが重要です。
弱点の特定
受験科目ごとに、得点の低かった分野や範囲を特定します。特に重要度の高いテーマや概念、解法に焦点を当てましょう。 間違えた問題に共通する要素やパターンを特定し、特定の問題形式や難易度に苦手意識があるか、特定のタイプの誤答が多いかを確認しましょう。
対処法の検討
教材や参考書を活用して、弱点の分野や範囲を復習しましょう。基本的な概念や知識を再確認し、不明な点や誤解を解消します。 また、過去問や模擬試験を使って、弱点の分野や問題形式を練習しましょう。反復練習を通じて、解答方法や戦略を磨くことが重要です。 教師や家族、友人に質問したり、解説を聞いたりすることでも理解を深めることができます。
長期的な計画の立て方
弱点の対処には時間と努力が必要です。長期的な学習計画を立て、定期的な復習や弱点の克服に取り組みましょう。 スケジュールを立てて、弱点の分野や範囲に十分な時間を割くことが重要です。短期的な集中学習や反復練習を繰り返すことで、徐々に弱点を克服していきましょう。
合否判定が悪くても最後まであきらめない人が勝つ
模試の合否判定が悪かった場合は、落ち込んでしまう受験生も多いでしょう。しかし、模試の結果はあくまでも目安です。受験本番の合否を決定づけるものではありません。もちろん、合否判定は合否の可能性を図るうえで参考になりますが、もっと重要なのは試験の内容を確認することです。
模試のたびに、自分の弱点やケアレスミスの原因を見つけて改善していけば、徐々に成績が上がり、合否判定もおのずと上がってくるでしょう。ただ、大学受験は最後まで結果がわからないものです。たくさんの模試で合否判定Aだった大学に落ちる受験生もいれば、合格判定がEだった大学でもあきらめずに勉強し続け、最後に合格を勝ち取る受験生もいます。
長丁場となる大学受験では、合否判定などを見て心折れそうになる場面も多いかもしれません。しかし、そこで落ち込まずに最後まであきらめない受験生が合格をたぐり寄せることができます。模試判定に一喜一憂するのではなく、間違った問題を確実にマスターしていくことが近道です。最後まであきらめず、志望校合格に向けて前進し続けましょう。