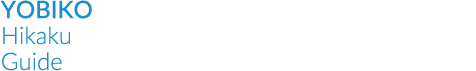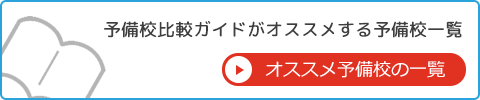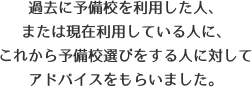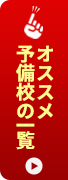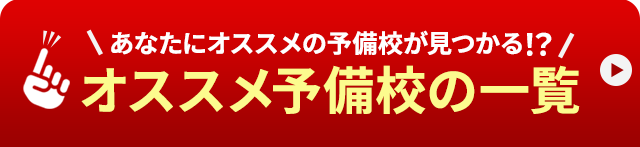大学受験塾はいつから通うべきか?中高一貫校や国立大学受験などパターン別に解説

「高1だからまだいいよね」「高3の部活が終わってからでも間に合うかな?」と大学受験のための塾に通い始める時期についてお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
結論、大学受験をするのであれば、できるだけ早く塾に通い始めるに越したことはありません。
自宅での独学と塾とでは、学習効率に大きな差が生まれます。
今回は、大学受験塾にはいつから通うべきなのか、そもそも塾に行くべきなのか、自分に合った塾の選び方などについてまとめました。
記事を最後までチェックすれば、いつからどの塾に通えばいいのかが見えてきますよ。
大学受験塾はいつから通うのがベスト?
ところで、大学受験塾へ行き始めるのはどのタイミングがベストなのでしょうか?
結論、塾へ行き始めるタイミングが早いに越したことはありません。つまり高校1年生から塾に行き始めるのがベストです。
ここでは、高1、高2、高3の3段階に分けて、塾で受験準備を始めるのにベストなタイミングを探ってみましょう。
「大学受験塾はいつから通うべき?」の答えは「高1から」
結論からいえば、塾に行き始めるベストタイミングは高1です。
大学受験問題は、どんな難問でも高校で履修する基礎的な学習内容がベースとなっています。つまり、大学受験で合格を勝ち取るには「基礎を早いうちからしっかりと固めることが必要不可欠」なのです。
苦手な科目や単元があると、理解が追い付かず勉強が捗らない場合もあるでしょう。しかし、まだ高1であれば時間があるため、塾で高校授業の先取りや復習ができ、理解が追い付かない箇所を一つずつクリアしながらゆとりを持って確実に基礎固めができます。
基礎固めがしっかりと習慣化していくことで、少し難しい応用問題や難関大学の受験問題を解く力もつくことが期待できるでしょう。特に、国公立大学や難関大学を目指す場合は、高1から塾で受験準備を行うのがおすすめです。
高2から塾に通えばまだ受験まで余裕がある
高2からの塾通いでも、まだ受験までには余裕があります。ただ、高1が終わった段階で学習の遅れがある場合は、高2の学習と並行して高1の復習を行う必要があります。
そのため、高1とは少々勉強の進め方の事情が異なります。
しかし、高2ならまだ受験本番まで時間があるので、これまでの学習の遅れや苦手な部分を着実に克服しつつ、受験準備を行う時間は十分にあるでしょう。
高3なら夏休みまでに塾に行こう
高3から塾に入る場合は、少し注意が必要です。受験まで残り1年未満となるため、すぐに受験準備に取りかからなければなりません。
高1・高2までの履修内容で学習の遅れがある場合は、かなりハイペースでその部分の復習を行いつつ、受験本番に向けた準備も同時進行で行わなければなりません。
また、9月に入ると大学入試共通テストの出願が始まります。それまでに苦手分野を克服し、受験問題を解けるレベルの学力をつけましょう。それに間に合うラストチャンスは、夏休み。特に、大きな弱点がある場合は、高3のはじめから塾に行くほうがいいでしょう。
塾・予備校の夏期講習については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:塾の夏期講習とは?日程や値段、夏期講習だけでも通えるのかを徹底解説!
このように、早い段階から塾に行けば余裕を持って受験準備ができます。しかし、家計の事情などから塾に行けないケースもあるでしょう。
その場合は、生徒自身の学習理解度や志望校などを考慮しながら、本人にとってベターなタイミングで塾に行き始めることをおすすめします。
目的や状況によっていつから大学受験塾に行くべきかは変わる?
ここまで「大学受験のために塾にはできるだけ早く通うべき」といった内容で解説をしました。
しかし大学受験の目的や状況は、人それぞれです。
例えば中高一貫校に通う学生、国立大学を目指す学生の場合、大学受験のために塾に通い始めるべき時期は変わってくるのでしょうか。
結論、どんな目的や状況であれ、早く塾に行き始めるに越したことはありません。
ここでは、中高一貫校に通う学生と国立大学を目指す学生が塾に行き始めるべき時期について解説します。
中高一貫校に通う学生の場合
中高一貫校で高校入試がない場合、中学生のうちから塾に通う方はあまりいないでしょう。しかし中学生の時点で授業についていけない場合は、塾に通うのも選択肢の1つ です。
中高一貫校の場合も、その他の場合と同じく、大学受験のためには高校1年生からの通塾がおすすめです。
中高一貫校によっては、中学生のうちから高校の内容を学習することがあります。その場合は、中学生のうちから塾に通うのも良いかもしれません。
しかし他の公立中学に通う生徒とは学習進度が異なるので、その辺も考慮しつつ塾を選ぶ必要があります。
国立大学を目指す学生の場合
国公立大学は私立大学と比較して、入試科目が多いです。具体的には、6教科8科目での入試が一般的です。
入試科目が多いと、対策にも時間がかかります。特に1科目でも苦手な単元があると、その単元を平均やそれ以上のレベルに引き上げるには大きな労力が必要となるでしょう。
よって国立大学を目指すのであれば、高校1年生の早い時期から塾に行くことをおすすめします。
国立大学を目指す場合も私立大学を目指す場合も、早い時期から塾に行くに越したことはありません。しかし国立大学の場合は、入塾時期が遅くなると、遅れを取り返せない可能性が高いです。
そもそも大学受験に塾は必要か?
「そもそも塾に行く必要ってある?」「独学でも良いのでは?」とお悩みの方も多いでしょう。
しかし結論、大学受験をするのであれば、塾には行くべきです。それもできるだけ早く行くべきです。
確かに塾には費用がかかります。しかし大学受験者の約6割が塾に通うなか、独学だけで大学受験を乗り切るのは、決して簡単ではありません。
そしてどの大学に進学できるかは、就職先などその後の人生を大きく左右します。
関連記事:大学受験で塾に行くべきかを決める3つの要素!注意点や行くと決めた後に取るべき行動も紹介
なかには独学で大学受験を乗り切る人もいる
確かになかには、塾に通うことなく、独学で大学受験を乗り切る人もいます。しかし独学がうまくいくのは、自分を律することに長けているごく一部の学生だけです。
スマホ、テレビ、ゲームなどあらゆる誘惑があるなか自宅で寝る前まで勉強をする能力や、分からない問題を自力で調べて解決できる能力、受験に間に合うようにスケジュールを立てる能力など、あらゆる能力が求められます。
上記を全てこなせる自信がある場合は、独学でも良いでしょう。しかし大半の高校生には、独学はおすすめしません。
「それでも独学で頑張りたい」と考えている方は、以下の記事もチェックしてみてください。
関連記事:大学受験の独学はきつい?無理?失敗する?おすすめ参考書や独学しやすい科目を紹介
「塾なし」で大学受験をする人の割合は約4割
大学合格者の約6割が、高校時代に塾に通っています。つまり塾に通わずに、独学で大学受験を乗り切った方の割合は、約4割です。
難関大学になればなるほど、塾に通う人の割合は高くなります。大学の偏差値が低ければ低いほど、塾に通う人の割合は低くなります。
大学によっては、塾に通っていた人の割合が9割を超えることもあるようです。
いずれにせよ、過半数は大学受験のために塾に通っています。よって塾に頼らない独学は、一般的な選択肢ではありません。
余程の事情がない限りは、塾に行くか行かないかではなく、いつから行くかで悩むべきです。
大学受験のために塾へ行くメリット
大学受験のために塾へ行くメリットは、主に以下の4つです。
- 最新かつ正しい受験情報を得られる
- 自分のレベルや志望校に応じた学習で効率的に勉強できる
- 学習面以外でもさまざまな受験サポートを受けられる
- 他の生徒から刺激を受けてモチベーションが上がりやすい
それぞれ詳しく見てみましょう。
最新かつ正しい受験情報を得られる
塾に行く最大のメリットは、最新かつ正しい受験情報を得られることです。
特に、過去の進学実績が高い大手塾や全国模試を実施する大手予備校は、常に最新の受験情報を収集しながら自塾が持つ情報のアップデートを行い、生徒や保護者に提供できる体制を整えています。
そのため、塾生やその保護者が受験情報をリサーチする時間を短縮できます。また、誤った受験情報に振り回されてしまうリスクも軽減できます。
自分のレベルや志望校に応じた学習で効率的に勉強できる
受験のプロである塾の適切な指導により、効率的に受験勉強ができることもメリットの一つです。
多くの塾では、大学入試共通テストや各大学の出題傾向のリサーチ・分析を随時行ったり、全国模試の結果などのデータから受験生の適性や弱点を分析したりしています。
分析結果をもとに、個々の生徒のレベルや志望校に応じた授業や個別サポートを行うため、生徒はより一層効率的な受験勉強が期待できるでしょう。
なお、個別サポートについては大手予備校や大規模塾ならチューター(塾生の学習サポートを行う人)が担当し、中小規模の塾であれば講師がその役割を果たすことが一般的です。
学習面以外でもさまざまな受験サポートを受けられる
塾に入ると学習面以外で以下のようなさまざまなサポートを受けられる点も大きなメリットです。
- 生徒や保護者への説明会・個別面談などで現在の入試制度や受験スケジュールの確認
- 出願の手続き
- 各大学の特徴についての説明
- 受験生一人ひとりの悩み相談に応じる
高校でも同様なサポートを受けることはできますが、塾は進学に特化した専門集団のため、より生徒に合った情報収集が期待できるでしょう。
他の生徒から刺激を受けてモチベーションが上がりやすい
複数の生徒が集まる塾では、同じ志を持つ他の生徒から刺激を受けやすくなる点もメリットです。
また、生徒同士で受験情報や勉強方法などの情報交換もできるため、一人で勉強するよりモチベーションが上がりやすいでしょう。
塾は、月謝や教材代などの費用が高額になりやすいため、お金を出す親からすれば独学で勉強してくれたほうが経済的には助かります。
しかし、高校生が独学で受験勉強を行い、なおかつ受験に関する情報収集などを行うのは、非効率的かつ精神的に大きな負担となりかねません。
その負担を軽減する役割を果たすのが塾であり、それを知る多くの生徒が大学受験に備えて塾に入っています。
関連記事:大学受験の独学はきつい?無理?失敗する?おすすめ参考書や独学しやすい科目を紹介
大学受験塾のタイプと自分に合った塾の選び方
ここからは、大学受験塾のタイプを「大学受験予備校」と「中小塾や個別指導塾」の2つに分けて、それぞれの塾の特徴について説明します。
大学受験予備校
大学受験予備校では、講師による集団授業(複数の校舎でサテライト授業を行うケースも含む)がメインとなっています。学習相談はチューターが個別に担当します。
大学受験予備校の最大のメリットは、受験に関する独自のデータベースを持ち、受験に勝つためのノウハウが豊富なことです。
また、レベルが近い人と切磋琢磨しながら勉強できたり、他校を含む多くの生徒と情報交換できたりする点もメリットでしょう。
大学受験予備校は、自分から講師に質問できる積極的な生徒や、集団授業で取り残されない程度に理解度が進んでいる生徒が向いています。特に、志が高く難関大学を目指せるレベルの生徒であれば、大学受験予備校が最適です。
しかし、集団授業型だと消極的なタイプや高学年でも基礎が固まっていない人は、授業についていけない恐れもあるため、別の塾に通うほうがいいかもしれません。
中小塾や個別指導塾
中小塾や個別指導塾では1対1、または2〜3人の生徒に1人の講師が指導を行う少人数形式を取っている傾向です。集団授業で取り残されそうな生徒でも、無理なく大学受験に必要な学力をつけることが期待できます。
個別指導塾には、大手予備校が運営しているケースと私塾など中小の塾がその形式で学習サポートを行っている場合などさまざまです。
前者の場合は、受験の情報やノウハウに関して大手予備校と同質のサービスを受けることができます。しかし、講師の指導レベルに差がある学生アルバイト、またはオンライン授業のケースもあるため、注意が必要です。
後者の場合は、実力のあるプロ講師から直接丁寧な指導を受けられるのが非常に大きなメリットです。しかし、講師と生徒との相性が悪いと思うように成績が伸びないデメリットもあります。また、受験情報についても大手予備校などに劣るケースも少なくありません。
以上の特徴をよく理解したうえで、より自分に合った塾を選ぶといいでしょう。
大学受験におすすめの塾・予備校3選
大学受験におすすめの塾・予備校は以下の3校です。
- 四谷学院
- 東進ハイスクール
- 森塾
それぞれ詳しく見てみましょう。
四谷学院
「四谷学院」は、集団授業と個別指導のダブル教育で大学受験合格を目指す予備校です。
集団授業では、科目別、そして能力別に受ける授業を選択できます。例えば国語の中でも得意な現代文は上級クラス、苦手な漢文は基礎クラスといった形での選択が可能です。
また55段階個別指導では、1科目を55段階に分けて、1つずつテストを実施します。55段階個別指導によって「分かると思っていたけれど解けない箇所」をあぶり出します。
四谷学院のダブル教育については、以下の動画が分かりやすいです。
関連記事:四谷学院はやめたほうがいい?予備校の特徴や口コミ・評判を解説
東進ハイスクール
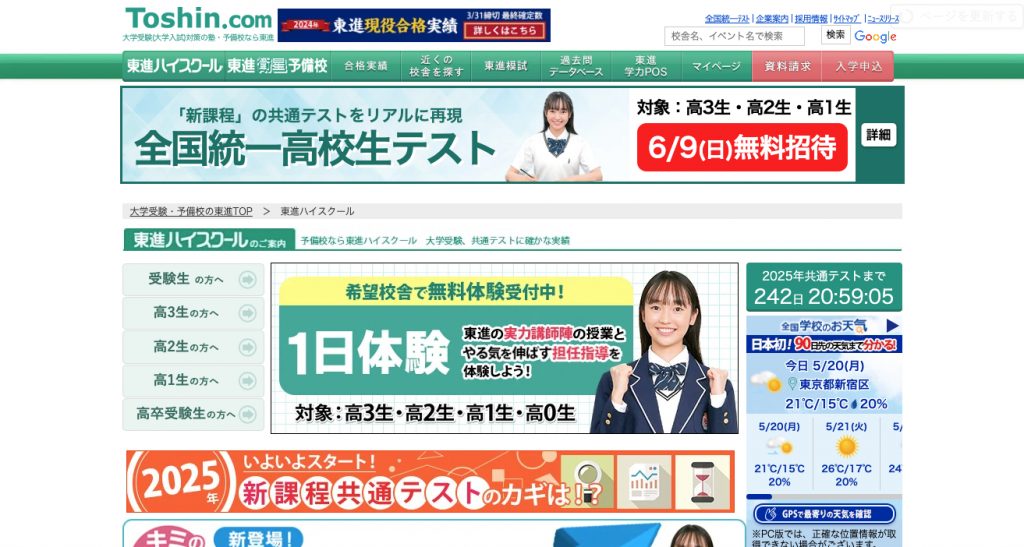
「東進ハイスクール」は、映像授業がメインの予備校です。
47都道府県に校舎があり、住んでいる場所にかかわらず、日本トップレベルの講師の授業が受けられる点が特徴です。
現在テレビでも大活躍中の林修先生が特に有名ですよね。
先ほど紹介した四谷学院のように、教室で集団で授業を受けるというスタイルではありません。よってある程度勉強の習慣がある方や、独学が得意な方に適した予備校となっています。
森塾

「森塾」は、学校の成績を上げることを目的とした個別指導塾です。
四谷学院や東進ハイスクールには、難関大学を目指す方も多いです。一方森塾では、これらの予備校よりももう少しゆったり、自分のペースで学習ができます。
よって「大学受験よりもまずは学校の授業についていけるようになりたい」と考えている方にもおすすめです。
森塾は、入塾後2学期以内に学校の定期テストで1回以上+20点に到達しなければ3学期の授業料が無料になる、学校成績保証制度を導入しています。
また国内トップクラスの超難関大学への合格者はいませんが、立教大学や学習院大学などへの合格者を輩出しており、森塾に通う高校生の志望大学合格率は90%を超えています。
関連記事:森塾の口コミ・評判はひどい?受験向きじゃない、宗教っぽいとの噂を検証
大学受験準備は早めがベスト!自分の性格や理解度に合わせて塾を選ぼう
大学受験塾にはいつから通うべきなのか、そもそも塾に行くべきなのか、自分に合った塾の選び方などについて解説しました。
大学受験の準備は、早いに越したことはありません。できれば、高1から塾で基礎固めをスタートすることがベストです。
ただ、大学受験塾には塾の形態によってそれぞれに特徴があり、人によってはミスマッチが生じることもあります。ミスマッチを防ぐには、自分の性格や、学習の理解度をまず正確に把握したうえで塾を選ぶのがおすすめです。
まずは、目星をつけた塾の説明会に足を運び、体験授業があれば受けてみましょう。実際に体験してみることで、自分が塾に入った後のイメージがつかみやすくなります。
大学受験におすすめの塾・予備校については「オススメ予備校一覧ページ」で紹介しています。興味がある方はぜひチェックしてみてください。